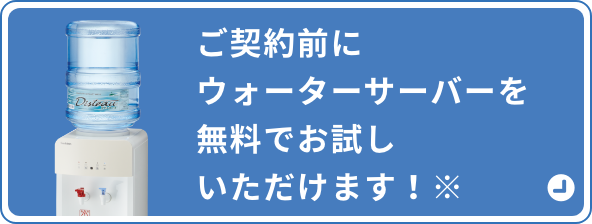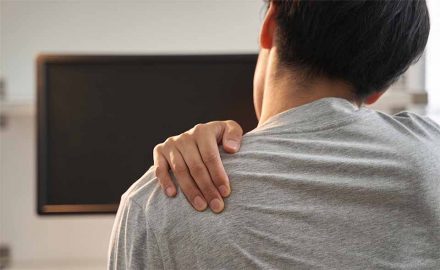- 法人様向けウォーターサーバー“ディスティオ”
- お知らせ
- コラム
- 水無月の由来や水無月という和菓子について
コラム
2017.06.25
水無月の由来や水無月という和菓子について

水無月の由来
水無月とは陰暦でいうところの「六月」を指す。水無月は、水の無い月と書くが、この無は「の」を意味する連体助詞の「な」であるため、水無月は「水の月」になる。陰暦六月は、田んぼに水を引く月であったため、水の月=水無月といわれるようになったと考えられている。
水無月という和菓子
京都には「水無月」という和菓子を食べる風習がある。水無月は白い三角形のういろうに小豆をのせたもので、これを食す日は6月30日と決まっている。この日には「夏越祓(なごしのはらえ)」という神事が行われる。この神事は、これまでの半年のけがれを払うことやその先の半年の無病息災を祈ることが目的であり、それに併せて食べられるのが水無月というわけなのだ。日本には、歳事に併せて和菓子を食すという風習がいくつかあるが、この水無月という和菓子に関しては京都以外の方だと「初めて耳にした」という方も少なくないかもしれない。
水無月が三角形である理由
水無月が三角形なのは、氷の欠片を模しているからだといわれている。その昔、庶民にとって氷は貴重なものであったため、そのような和菓子の作り方が生まれたのではないかという説もあれば、一方で暑気払いの氷として三角形にカットしたのではないかという説もある。また、白いういろうの上に小豆をのせるのは、厄除けのためだそうだ。水無月のように特別なときに食べる和菓子には、こんな風にいろいろな意味が込められているのかもしれない。