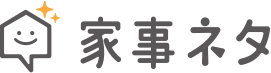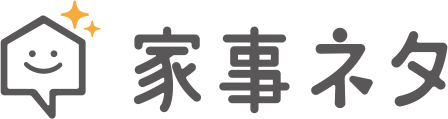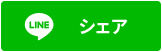O157はいつ流行するの?

O157が原因による食中毒は、おもに初夏から初秋(6月~10月)にかけて流行します。
食中毒の原因のひとつとしてよく知られている「O157(腸管出血性大腸菌)」は体内に侵入すると、腸管内でベロ毒素という「出血性下痢」を引き起こす毒素を作りだします。これにより激しい腹痛、下痢、そして血便などの症状を引き起こします。
O157は2008年から2017年にかけて、平均して毎年3,900名以上の人が国内で感染しています。O157は細菌で、細菌性食中毒の多くは初夏から暑さの残る初秋にかけて頻繁に発生していますが、暑さがピークを迎える8月、9月に最も多く発症しています。
暑さと湿気を好む細菌は、暑くなればなるほど活発に繁殖するようで、この時期に重なりあいやすい以下の3つの条件により、細菌性の食中毒(O157など)が頻繁に発症するようです。
- 細菌性の食中毒菌が増えるのに適した気温であること。
- 人の体力が低下していること。
- 食品などの不衛生な取扱い。
2017年8月に埼玉県と群馬県の総菜店で販売されたポテトサラダを食べた人がO157に集団感染したというニュースは記憶に新しいところです。このように、初夏から初秋(特に8月、9月)はO157の感染リスクが高まる時期なので十分に注意する必要があります。
インフォメーションプラス
O157は口から感染する

イメージ
O157は細菌が口から入ることで感染します。菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染した人の“便に含まれる菌”が口から入ることによって感染します。感染した人と話をしたり、咳やくしゃみ、汗などでは感染しません。
また、一般の食中毒は10万~100万個の菌数で発症するといわれていますが、O157は100個程度でも感染するといわれています。
「人から人」への感染予防は手洗いが基本

人から人への感染を予防する基本は手洗いです。
排便後や食事前、調理前にはせっけんで手指を洗って流水できれいに流し落とします。
サラヤさんのホームページで紹介されている「衛生的手洗い」では、大腸菌を手指に塗布し、「洗って」「ふいて」「消毒」の各工程での菌の減り具合を調べた結果が以下のように紹介されています。
- 石けんで手を洗うだけで菌数が1/100程度に減少。
- さらに、ペーパータオルで水分や汚れをふき取るようにすると1/10程度に減少。
- さらに、アルコールで手指消毒をするとほぼ“検出限界以下”に。
このような「洗う」「ふく」「消毒」のプロセスは、O157対策でもかなり有効であることがわかりますね。
家庭でできる食品からの感染予防ポイント

以下は厚生労働省で推奨されている対策です。O157などの細菌性の食中毒が流行する時期には、特に以下の対策に気を配りましょう。(厚生労働省HPより一部抜粋)
1.食品の購入 について

肉汁がもれても他の食材などにつかないようにしましょう
- 肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮な物を購入しましょう。
- 表示のある食品は、消費期限などを確認し、購入しましょう。
- 肉汁や魚などは水分がもれないようにビニール袋などにそれぞれ分けて包み、持ち帰りましょう。
- 特に、生鮮食品などのように冷蔵や冷凍などの温度管理の必要な食品の購入は、買い物の最後にし、購入したら早めに帰るようにしましょう。
2.家庭での保存

食品はすぐに冷蔵庫に保存する
- 冷蔵や冷凍の必要な食品は、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
- 冷蔵庫の詰めすぎに注意しましょう。
- 冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に維持しましょう。
- 細菌の多くは10℃で増殖がゆっくりとなり、-15℃では増殖が停止しますが、細菌が死ぬわけではありませんので早めに使いきるようにしましょう。
- 肉や魚などはビニール袋や容器に入れ、冷蔵庫の中の他の食品に肉汁などがかからないようにしましょう。
- 肉、魚、卵などを取り扱う時は、取り扱う前と後に必ず手を洗いましょう。
- 食品を流し台の下に保存する場合は、水漏れなどに注意しましょう。
3.調理

野菜はよく洗ってから調理する
- 井戸水を使用している家庭では、水質に十分注意してください。
- 手を洗いましょう。
- 生の肉、魚、卵を取り扱った後には、手を洗いましょう。
- 途中でペットなどの動物に触ったり、トイレに行ったり、おむつを交換したり、鼻をかんだりした後の手洗いも大切です。
- 生の肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べる物や調理の済んだ食品にかからないようにしましょう。
- 生の肉や魚を切った後、その包丁やまな板を洗わずに、続けて果物や野菜など生で食べる食品や調理の終わった食品を切ることはやめましょう。
- 生の肉や魚を切った包丁やまな板は、洗ってから熱湯をかけたのち使うことが大切です。
- 包丁やまな板は、肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて、使い分けるとさらに安全です。
- ラップしてある野菜やカット野菜もよく洗いましょう。
- 冷凍食品など凍結している食品を調理台に放置したまま解凍するのはやめましょう。室温で解凍すると、食中毒菌が増える場合があります。
- 解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで行いましょう。また、水を使って解凍する場合には、気密性の容器に入れて流水を使います。
- 料理に使う分だけ解凍し、解凍が終わったらすぐ調理しましょう。
- 解凍した食品をやっぱり使わないからといって、冷凍や解凍を繰り返すのは危険です。冷凍や解凍を繰り返すと食中毒菌が増殖する場合もあります。
- 包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジなどは、使った後すぐに、洗剤と流水で良く洗いましょう。
- ふきんのよごれがひどい時には、清潔なものと交換しましょう。漂白剤に1晩つけ込むと消毒効果があります。
- 包丁、食器、まな板などは、洗った後、熱湯をかけたりすると消毒効果があります。たわしやスポンジは、煮沸すればなお確かです。

熱の伝わり方に注意
- 加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。
- 加熱を十分に行うことで、もし、食中毒菌がいたとしても殺菌することができます。目安は中心部の温度が75℃で1分間以上加熱することです。
- 料理を途中でやめてそのまま室温に放置すると、細菌が食品に付いたり、増えたりします。途中でやめるような時は、冷蔵庫に入れましょう。
- 再び調理をするときは、十分に加熱しましょう。
- 電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使い、調理時間に気を付け、熱の伝わりにくい物は時々かき混ぜることも必要です。
4.調理後

室温での長期放置は禁物
- 清潔な手で、清潔な器具を使い、清潔な食器に盛りつけましょう。
- 温かく食べる料理は温かく、冷やして食べる料理は冷たくしておきましょう。目安は、温かい料理は65℃以上、冷やして食べる料理は10℃以下です。
- 調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置してはいけません。 例えば、O157は室温でも15~20分で2倍に増えます。
- 乳幼児やお年寄りのO157などの腸管出血性大腸菌感染症は症状が重くなりやすく、死亡率も高くなります。これらの年齢層の人々には加 熱が十分でない食肉などを食べさせないようにした方が安全です。
5.残った食品
- 残った食品はきれいな器具、皿を使って保存しましょう。
- 残った食品は早く冷えるように浅い容器に小分けして保存しましょう。
- 時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てましょう。
- 残った食品を温め直す時も十分に加熱しましょう。目安は75℃以上です。
- 味噌汁やスープなどは沸騰するまで加熱しましょう。
- ちょっとでも怪しいと思ったら食べずに捨てましょう。
常に新しい情報をチェック!
厚生労働省の「腸管出血性大腸菌O157等による食中毒( http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/daichoukin.html)」ページでは常に新しい情報が公開されています。ご家庭での対策を含め一度チェックすることをおすすめします。
<参考文献>
国立感染症研究所「腸管出血性大腸菌感染症」
https://www.niid.go.jp/niid/ja/ehec-m/ehec-iasrtpc/8022-459t.html
国立感染症研究所「腸管出血性大腸菌感染症報告数」
https://www.niid.go.jp/niid/images/iasr/2018/05/459tt01.gif
厚生労働省「腸管出血性大腸菌Q&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html
厚生労働省「我が国おける食中毒の発生状況と課題」
http://www.anan-zaidan.or.jp/pages/110620-1.pdf
上尾市医師会「病原性大腸菌O157を予防するために」
http://www.ageomed.com/index.php?action=o157:index