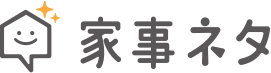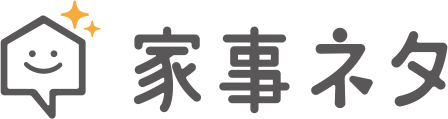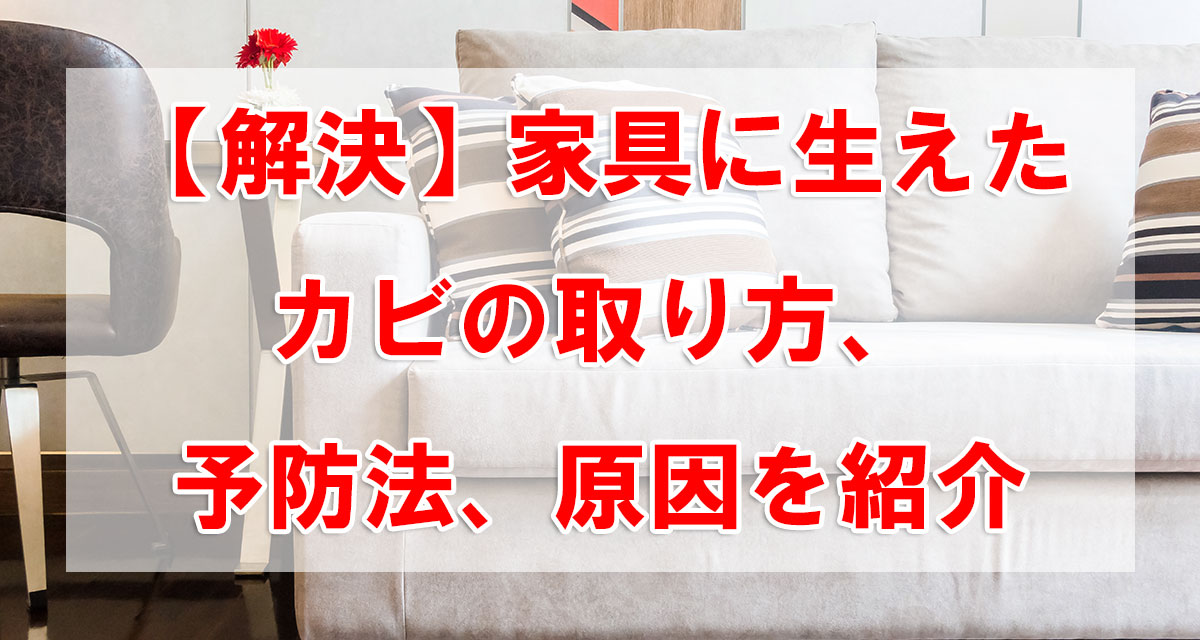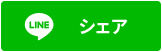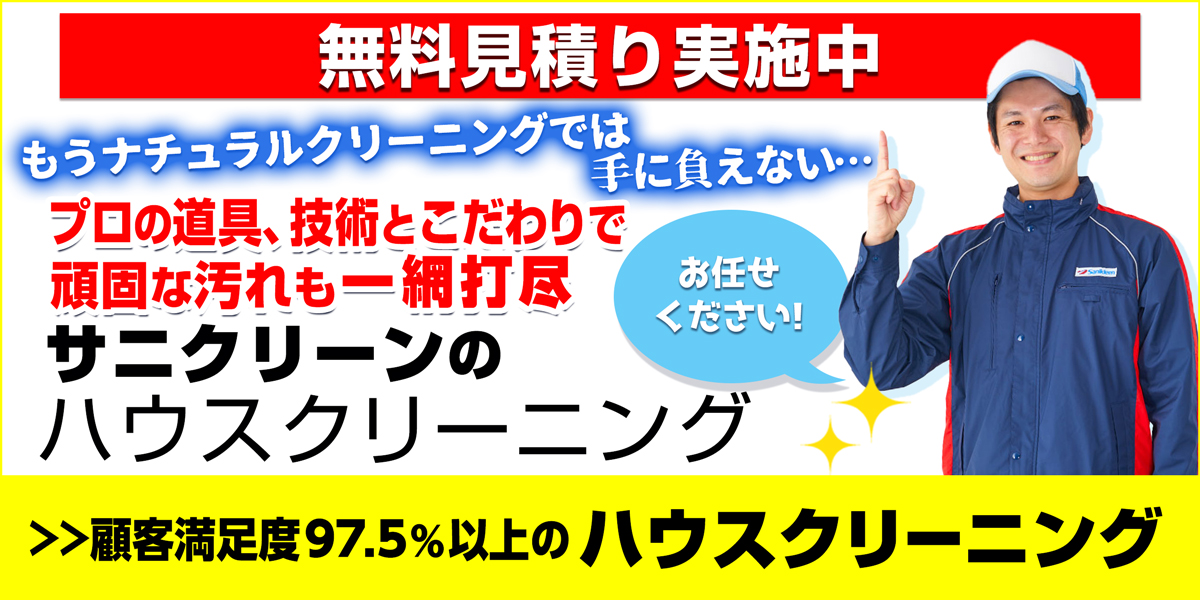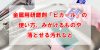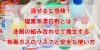家具にカビが生える主な原因は、通気不足による湿気と、カビの栄養源となるホコリなどの蓄積によりカビの繁殖条件が整ってしまうことです。家具のカビ落としは、木材や布など専用の「カビ取り剤」や「消毒用エタノール」で行います。また、家具のカビ予防では「家具と壁の間をあける」「ものを詰め込みすぎない」など、主に通気性を良くすることが求められます。
そこで、このコラムでは、家具にカビが生える原因と、取り方(掃除方法)、予防法を紹介していきます。また、カビが生えにくい家具の選び方なども紹介していきます。
家具にカビが生える原因
「気がついたら家具の裏に白っぽい斑点があった」「引き出しを開けたらカビ臭い」といった経験はありませんか。
湿気の多い日本の家庭では、多くの方が家具のカビに悩まされています。実際、住宅機器メーカーが行った調査でも、自宅のカビに困った経験がある人は7割を超えるという結果が出ています。
そこで、ここでは家具にカビが発生する原因と、注意すべき条件や時期について紹介します。
空気中に漂う「カビの胞子」が繁殖原因
空気中には「カビの胞子」が漂っています。
胞子は目に見えませんが、ほとんどの場所に存在しています。そして、この胞子が繁殖に適した環境を見つけたとき、増殖がはじまりカビとして目に見えるようになるのです。
カビが繁殖する環境(条件)
カビは、「気温25〜28℃」「湿度80%以上」「栄養源(ホコリなどの汚れ)」という3つの条件がすべて揃うと繁殖します。
これが、先ほど紹介した「胞子が繁殖に適した環境」ということになります。家具にカビが発生する場合、多くは表面やすき間に付着したホコリや皮脂汚れを栄養源として繁殖します。

特に、木材や布製品などの吸湿性の高い素材は湿気を溜め込みやすく、カビの胞子が増殖する「温床」となりやすいため注意が必要です。
【参考】<家事ネタ>月2回のお風呂掃除でカビを防止する。浴室をカビさせないコツと習慣
家具がカビやすい場所と条件
家具の中でも、特にカビが発生しやすいのが壁にぴったりとつけている「棚」や「タンス」など、通気が悪くなりがちな家具の裏側や中(内部)です。

家具と壁にすき間がないと空気の流れが生まれず、家具の裏側、または中に湿気がこもってしまいます。そこに気温やホコリなどの栄養源が加わると、カビにとっての絶好の繁殖環境となります。
エネルギー機器メーカーが実施した調査によると、「家具の裏側や押し入れ、部屋の壁に発生するカビに悩んでいる」と回答した人は、全体の1割程にのぼるとの結果が出ました。これらの場所は一見目立ちにくいものの、実際にはカビの発生リスクが高い環境となりますので注意が必要です。
梅雨時期や夏場など、季節ごとの注意点
日本の気候においてカビが特に発生しやすいのは、「梅雨」や「夏場」のように湿度が高くなる季節、そして「冬場」の結露シーズンです。

気象庁のデータによると、2019年から2023年までの6月と7月の平均湿度は常に70%を超え、月によっては80%以上になることもあります。梅雨や夏の高温多湿な環境は、カビの繁殖にとって最適な条件がそろう時期といえるでしょう。
また、見落とされがちなのが冬場の結露による湿気です。室内が暖房で暖められ、外気との温度差が大きくなることで、窓や家具の裏側などに結露が発生します。この水分が乾かずに残ると、湿気を好むカビの温床となってしまいます。窓のパッキン部分、家具の裏側の木材部分は注意が必要です。
建材メーカーが実施した調査では、結露に悩む人の約7割が「カビの原因になる」と感じていて、「結露対策はそのままカビ対策につながる」と考える人が多いことも分かっています。
家具のカビの間違った取り方
家具にカビを見つけたとき、どう処置すればいいか分からない方は多いと思います。
正しい知識がないまま対応すると、家具を傷め、かえってカビを広げてしまう恐れもあります。
最も避けるべきことは、濡れた雑巾でゴシゴシこすることです。これではカビの胞子が空気中に舞い上がり、他の場所での繁殖を助長させてしまう可能性があります。
また、カビに直接「塩素系漂白剤」を使うのも避けましょう。家具を傷め、変色や塗装の剥がれを引き起こす恐れがあります。
同じように、カビに直接アルコールスプレーを大量に吹きかけるのも避けましょう。変色や塗装の剥がれを引き起こす恐れがあります。
家具の素材ごとの正しいカビの取り方
家具にカビが生えたときに最も重要なのが、素材に合った方法で対応することです。
ここでは、木製、布製、革製といった素材ごとのカビ取り方法を紹介します。
タンスなどの「木製家具」に生えたカビの取り方
タンスやクローゼット、押し入れなどの木材に生えたカビは内部にまで根をはるため、放っておくと何度も再発してしまうことがあります。早めに対処しましょう。
<用意するもの>
・消毒用エタノール(または木材用のカビ取り剤)
・柔らかい布
・ゴム手袋
・扇風機(サーキュレータなど)
・防カビ剤
<カビ取りの手順>
(1)カビを取り除く
カビの範囲が広い場合は、消毒用エタノールや木材専用のカビ取り剤を布に染み込ませ、カビ部分を軽く拭き取ります。
※事前に目立たない場所で変色しないか確認しましょう。

(2)しっかりと乾燥させる
拭き取り後は、風通しの良い場所で乾燥させましょう。
また、自然乾燥が難しい場合は、扇風機などを利用して乾燥させます。

(3)防カビ対策を施す
完全に乾かしたら、「防カビ剤」を塗り再びしっかり乾燥させます。
消毒用エタノールなどの薬剤を使用する前には、目立たない場所で色落ちや変質がないか確かめましょう。また、作業中は十分な換気を行ってください。
ソファなどの「布製家具」に生えたカビの取り方
布製のソファや椅子、カーペットなどにカビが発生すると、繊維の奥にまで根をはり、再発リスクが高くなります。木材同様、発見したら早めに対処するようにしましょう。

<用意するもの>
・消毒用エタノール(または布用のカビ取り剤)
・柔らかい布
・ゴム手袋
・防カビスプレー
<カビ取りの手順>
(1)まずはしっかり乾燥させる
カビが生えた家具を風通しの良い場所に移動し、日光に当ててしっかり乾燥させます。
(2)洗えるカバーは洗濯+天日干し
取り外せるカバー類は洗濯してからしっかり天日干しをします。
(3)殺菌処理を行う
消毒用エタノールや布用のカビ取り剤を布につけカビを拭き取ります。素材が劣化する恐れがあるため、目立たない場所で事前にテストをしてから使いましょう。
(4)防カビ対策で仕上げ
しっかり乾燥させた後、防カビスプレーを使ってカビの再発を防ぎます。使用後はしっかり乾かしましょう。
「革製家具」に生えたカビの取り方
革製品は非常に繊細な素材であるため、木製や布製家具と比べて一層慎重な対応が求められます。

<用意するもの>
・革専用のカビ取り剤
・柔らかい布
・ゴム手袋
・扇風機(サーキュレータなど)
・防カビスプレー
・革専用の保湿剤(クリーム)
<カビ取りの手順>
(1)革専用カビ取り剤でカビを除去
柔らかい布に、革専用のカビ取り剤をつけカビのある部分を拭き取ります。
カビ取り剤を使用する前には必ず事前に目立たない箇所で試してから使いましょう。変色や風合いの変化が起きないかを確認してください。
(2)しっかり乾燥させる
カビを取り除いたあとは、風通しのよい場所で自然乾燥させます。移動が難しい場合は扇風機を使い乾燥させます。
革は強い日光に弱く変色や劣化の原因になるため、陰干しするようにしましょう。
(3)保湿と保護で仕上げる
乾燥後は、革専用の保湿剤(クリーム)を塗ります。
革製品の処置は難しいので、個人での作業が難しいと感じたらプロのクリーニングサービスに依頼しましょう。
カビ取りや予防に使う洗剤
ここでは、カビの除去や予防で使用される代表的な洗剤について紹介します。
一見すると効果がありそうでも、実際には十分な効果が得られないケースもあるため、使用する際はそれぞれの特徴や用途を正しく理解しましょう。
「消毒用エタノール」の特性とカビ対策への有効性

消毒用エタノールは、カビの細胞膜に作用し、たんぱく質を変性させ不活化させます。
特に、70〜80%の濃度が最も効果があるといわれています。
漂白効果はありませんが、木材・布・革など、さまざまな素材に使えます。ただし、色落ちや変質の可能性もあるため、必ず目立たない場所でテストを行ってから利用するようにしましょう。また、引火性があるため、火の近くでは使用しないようにしましょう。
「中性洗剤」の特性とカビ対策への有効性
中性洗剤は「界面活性剤」の働きにより、カビの温床となる「皮脂汚れ」や「石けんカス」を取り除きます。
ただし、表面的なカビを取り除く(拭き取る)ことはできるものの、中性洗剤にはカビそのものを死滅させる殺菌作用はありません。

「カビ取り剤」の特性とカビ対策への有効性
カビ取り剤は、黒カビなどの根をはった頑固なカビに対しても有効な成分(次亜塩素酸ナトリウムなど)を含んでおります。次亜塩素酸ナトリウムは強力な酸化力でカビの細胞壁、色素を破壊するので見えない状態(=漂白)にする効果があります。
また、最近では木材・布・革など、素材ごとに適切なカビ取り剤が発売されています。素材のダメージを防ぐため、素材に適したカビ取り剤を選びましょう。
防カビ剤(防カビスプレー)の特性とカビ対策への有効性
防カビ剤を、カビが発生しやすい場所にあらかじめ処置することで、カビの繁殖をある程度抑えることができます。
スプレータイプであれば、必要な場所に吹きかけるだけなので手間なく使えます。木材用、布用、浴室用など、素材や使用シーンに特化した防カビ剤も多いことから適切な商品を選びましょう。

ただし、すでにカビが生えている場合は、カビを取り除いてから使用するようにしましょう。
どうしても家具のカビが落ちない場合の対処法(プロへ依頼する)
いくら丁寧に処置をしても、個人ではカビを除去できないケースがあります。
特に、カビを除去した後に「黒ずみが残る」「白っぽく変色した」といった状態であれば、カビが素材の内部まで深く浸透しており、表面を取り除くだけでは再発する恐れがあります。
たとえば、木製家具はカビが木の繊維の奥まで根をはると、変色や質感の変化が起こりやすくなります。このような状態では、市販の洗剤では対応が難しく、専門的なクリーニングや補修が必要になる場合があります。また、状況によっては修復ではなく買い替えを検討することも必要になります。
また、布製ソファやマットレスなどの「吸湿性の高い素材」では、カビが目に見える部分からは消えていても、内部に残って再発するリスクが高いものです。何度も同じ場所にカビが発生する場合は、個人での対処が限界であるサインともいえます。
このような場合は、早めにプロのクリーニング業者に相談しましょう。
家具のカビの繁殖を防ぐ方法(予防方法)
せっかくカビを取り除いても、環境がもとのままなら、カビの再発を招く恐れがあります。そこで、ここでは家具にカビを生えさせないための方法(生活習慣)を紹介します。
通気性を見直すことで家具のカビを予防する
家具が壁にぴったりくっついていると、風通しが悪くなるため湿気が溜まりやすくなってしまいます。
そこで、通気性を高めるために家具と壁の間にすき間を作りましょう。また、家具の上に物を積みすぎない、引き出しや扉をときどき開放するなど、風通しを意識し湿気を逃がすようにしましょう。

また、家具ではありませんが、マットレスや布団を床に置きっぱなしにすると、マットレスそのものや床面にカビが生えることがあります。起床時にはマットレスを立てかける、マットレスや布団の下に「すのこ」を敷くなど、風通しが良くなる工夫をしましょう。

企業の調査によれば、「マットレスにカビが生えたという」経験がある人は、およそ2人に1人にのぼっています。
こまめな部屋の換気で家具のカビを予防する
カビの発生を防ぐためには、先ほどと同じく適切な換気による湿気対策が欠かせません。
単に窓を開けるだけでなく、部屋の対角線上にある2か所以上の窓を開けることで空気の流れをつくり、部屋全体にこもった湿気を外へ逃がすことができます。このような換気は室内の乾燥だけでなく、カビの胞子を屋外へ排出する効果も期待できます。

さらに、24時間換気システムが備わっている住宅であれば積極的に活用することが重要です。常に空気が循環している状態を保つことで、湿度の上昇が抑えられるのでカビの発生リスクを低減します。
また、クローゼットや押し入れなどの収納スペースも空気の流れがないところなので、人がいない日中には扉を開けておいて内部の空気を入れ替えるようにしましょう。ただし、在宅中は人の動きなどによりホコリがたちやすいため閉じておくようにしましょう。

普段の掃除で家具のカビを予防する
普段の掃除で、カビの栄養分(エサ)となるホコリなどの汚れを取り除くことは効果的な予防策となります。
家具の上や裏側にはホコリが溜まりがちです。また、ソファなどは表面にもホコリが溜まります。ペーパーモップや掃除機などでこまめにホコリを取り除きましょう。

家具の移動によるカビ対策
気分転換を兼ねて家具の配置を見直すことは、カビ対策としても有効です。
家具の位置を定期的に変えることで、空気の流れが生まれ通気性が向上します。また、家具の裏側などを掃除する機会が生まれるので、カビの発生源となるホコリなどの栄養分を取り除くことができます。
「詰め込みすぎ」と「除湿ケア」でカビ対策
衣類などを収納する家具の中のカビを防ぐためには、「詰め込みすぎない」ことが大切です。収納物がぎゅうぎゅうに詰まっていると通気性が悪くなり、湿気がこもってカビが発生しやすくなります。

特に、湿気を吸いやすい衣類や布団の近くには、除湿剤を置き湿度の上昇を抑え、カビの繁殖リスクを下げましょう。
家具のカビが引き起こす健康リスク
家具にカビが生えたと聞くと、見た目や臭いの問題をまず思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実は、カビは住まいの汚れ以上に「健康リスク」として警戒すべき存在なのです。ここでは、私たちがよく目にする「黒カビ」の健康リスクについて紹介します。
黒カビの正体は「クラドスポリウム」
私たちがよく目にする黒カビは、「クラドスポリウム」というカビの一種です。
胞子を空気中に放出し、湿度が高く栄養分(ホコリや皮脂、ロドトルラ菌など)が豊富な環境で繁殖します。
黒カビがもたらす主な健康被害
黒カビが放つ胞子が空気中に舞い、それを吸い込むことで、さまざまな体調不良を引き起こすといわれています。

(1)アレルギー性鼻炎や咳、くしゃみ
黒カビの胞子がアレルゲンとなり、吸い込むことで鼻水やくしゃみ、咳などの症状が出ることがあるといわれています。これらは花粉症やハウスダストに似た症状ですが、黒カビが原因の場合は、梅雨時期や夏場、あるいは換気が不十分な環境で悪化しやすい傾向があるとも考えられています。
(2)喘息の発症
黒カビの胞子は気道を刺激し、喘息の発作を引き起こす可能性があるといわれています。もともと喘息を持っている方や、小さなお子さん、高齢者はより影響を受けやすいため要注意です。
(3)夏型過敏性肺炎
夏型過敏性肺炎は、胞子を吸い込むことで発症する健康被害です。
また、カビの中でも「トリコスポロン」というカビが原因で引き起こされる症例が数多く紹介されています。夏場に多く発症し、発熱や咳などの症状があらわれる恐れがあります。
ちなみに、エアコンの中の黒カビが原因となって、夏型過敏性肺炎になる場合があるようです。家具のカビとともに、夏場はエアコン内部のカビにも注意が必要です。
【参考】<家事ネタ>梅雨や夏に咳が出る…エアコンや浴室のカビが原因の「夏型過敏性肺炎」
(4)皮膚トラブル・アトピー性皮膚炎の悪化
黒カビが皮膚トラブルの直接的な原因になる恐れがあるといわれています。
カビが生えにくい家具選びのポイント
最近では「家具を買うときにカビの生えにくさを重視する」という声も多く聞かれるようになっています。
そこで、ここでは素材選びから設置方法、収納の工夫まで、カビが生えにくい家具選びの方法を紹介します。
(1)湿気に強い素材を選ぶ
ウレタン塗装やラッカー仕上げの家具は湿気の吸収を抑える効果が期待できます。また、桐材の家具は放湿性にも優れているといわれています。
(2)通気性の良いデザインを選ぶ
脚つきの家具は床との間にすき間ができ、空気の流れが良くなります。また、背面が開いている棚や収納系の家具は、壁との接触面が少なくなり、湿気がこもりにくくなります。

まとめ|家具のカビを予防して安心な暮らしを手に入れよう
家具などに生えたカビは、気づかないうちに繁殖し見た目の劣化だけでなく、住む人の健康も脅かす存在になります。実際に、WHO(世界保健機関)でも室内の湿気やカビは深刻な公衆衛生問題とされており、住まいの衛生管理は「健康づくり」の一環と考えられています。
そこで、掃除や換気により、カビが繁殖しにくい環境を整えていきましょう。また、カビが生えてしまった場合であっても正しい知識のもと、効果的な掃除を実践しましょう。大切な家具をカビから守ることは、家族を健康被害から守ることにもつながるのです。
Q&A|家具のカビに関する疑問
Q1.家具にカビが生える主な原因は何ですか?
A.湿気と通気不足、ホコリや皮脂などの栄養源がカビの繁殖条件を整えるためです。
Q2.家具に生えたカビはどうやって掃除すればいいですか?
A.素材に応じたカビ取り剤や消毒用エタノールを使い、やさしく拭き取り、しっかり乾燥させます。
Q3.木製家具に塩素系漂白剤を使っても大丈夫ですか?
A.木材を傷め変色させる恐れがあるため、できるだけ塩素系漂白剤の使用は避けてください。
Q4.カビの再発を防ぐために重要なことは何ですか?
A.通気性の確保、湿気の管理、定期的な掃除が再発防止に効果的です。
Q5.エタノールはどの濃度がカビに効果的ですか?
A.70~80%の消毒用エタノールがカビの殺菌に最も効果的とされています。
Q6.カビが発生しやすい家具の場所はどこですか?
A. 壁に密着した棚やタンス、押し入れなど通気性の悪い裏側や内部です。
Q7.布製家具にカビが生えた場合、どう対応すればよいですか?
A.まず日光でしっかり乾燥させカバーは洗濯し、エタノールや布用カビ取り剤で拭き取ります。
Q8.家具の配置換えがカビ対策になるのはなぜですか?
A.空気の流れが生まれ通気性が改善され、掃除によってカビの栄養源を取り除けるからです。
Q9.カビが落ちないときはどうすればいいですか?
A.内部にカビが根をはっている可能性があるため、専門業者に相談するのが望ましいです。
Q10.カビによる健康被害にはどんなものがありますか?
A.アレルギー性鼻炎、咳、喘息、夏型過敏性肺炎、皮膚炎など、さまざまな影響があります。
<参考文献>
文部科学省「カビ対策マニュアル 基礎編」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sonota/003/houkoku/08111918/002.htm
厚生労働省「カビ及びダニ対策について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/150522.pdf