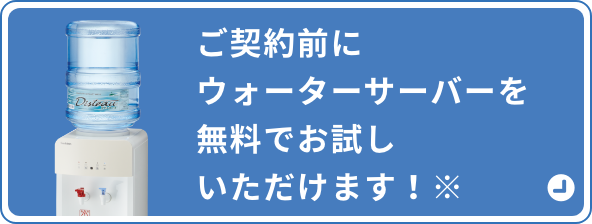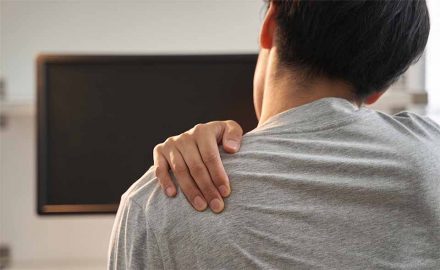- 法人様向けウォーターサーバー“ディスティオ”
- お知らせ
- コラム
- 水道の歴史を紐解く
コラム
2016.05.20
水道の歴史を紐解く

世界で最初の水道
生きていく上でなくてはならないお水。それは今も昔も変わらない。そんな水を私たちに送り届けてくれる水道には、いったいどんな歴史があるのだろうか。世界でもっとも早く水道が生まれたのは古代ローマといわれている。約2300年も前の古代ローマでは水不足に悩み、それを解消する目的で水道橋が作られた。その水道橋によって山にある水源地から都市へと水を引くことができるようになった。
日本で最初の水道
日本において水道の先駆けとなったといわれているのが、今から500年以上前に神奈川県の小田原城下に作られた「小田原早川上水」だ。徳川家康が江戸に神田上水を引いたのも、小田原早川上水の影響だとされている。その後、玉川上水や千川上水といった水道が作られ、江戸の人々の生活にだんだんと水道という存在が浸透していった。こうした水道の整備は、都市の発展になくてはならない要素でもあった。
発展を続ける江戸水道
18世紀初頭の江戸には、約100万人もの人々が生活していた。その当時、世界的な都市であるロンドやパリの人口は、それぞれ約50万人だったため、それと比較するとどれだけ多くの人が江戸に集まっていたのかを知ることができる。そんな江戸の人々の生活を支えていたのが、前述の「神田上水」「玉川上水」「千川上水」、そして「青山上水」「三田上水」「亀有上水」の六上水だ。
このように世界的な規模を誇った江戸水道だが、当時の水道は重力だけに頼ったものであった一方で、欧州の水道にはすでにポンプによる圧力が用いられ、水道技術には大きな差があった。また、18世紀後半になると、パリの地下では下水道網が整備され、欧州の近代化をまざまざと見せつけられる格好となった。日本は水道先進国のひとつだが、その優れた技術も、一朝一夕には確立し得るものではなかった。