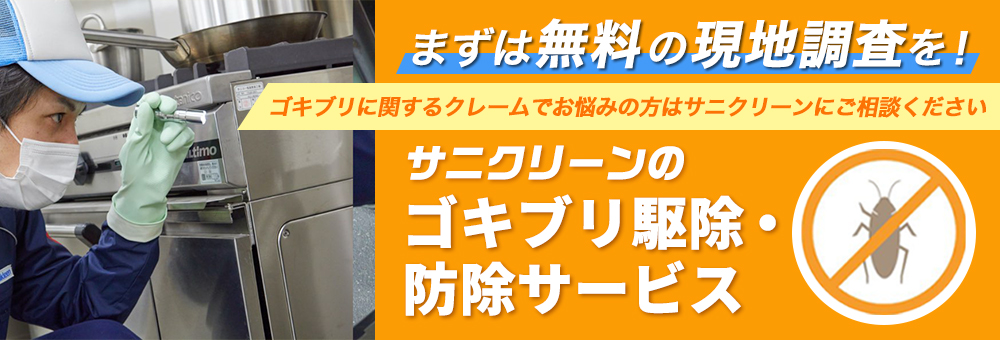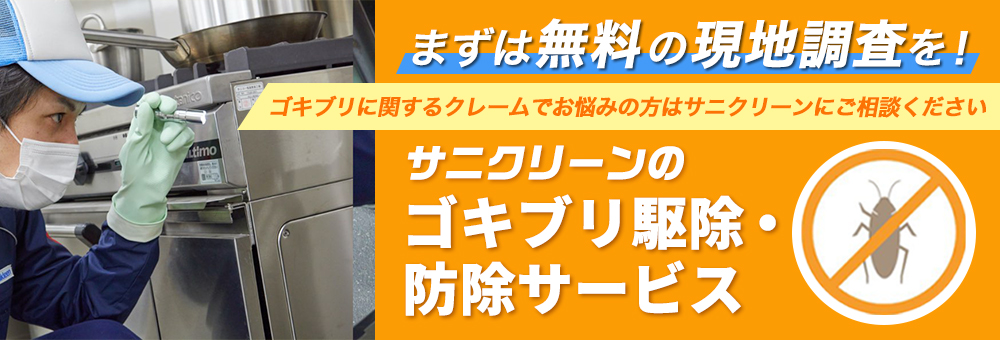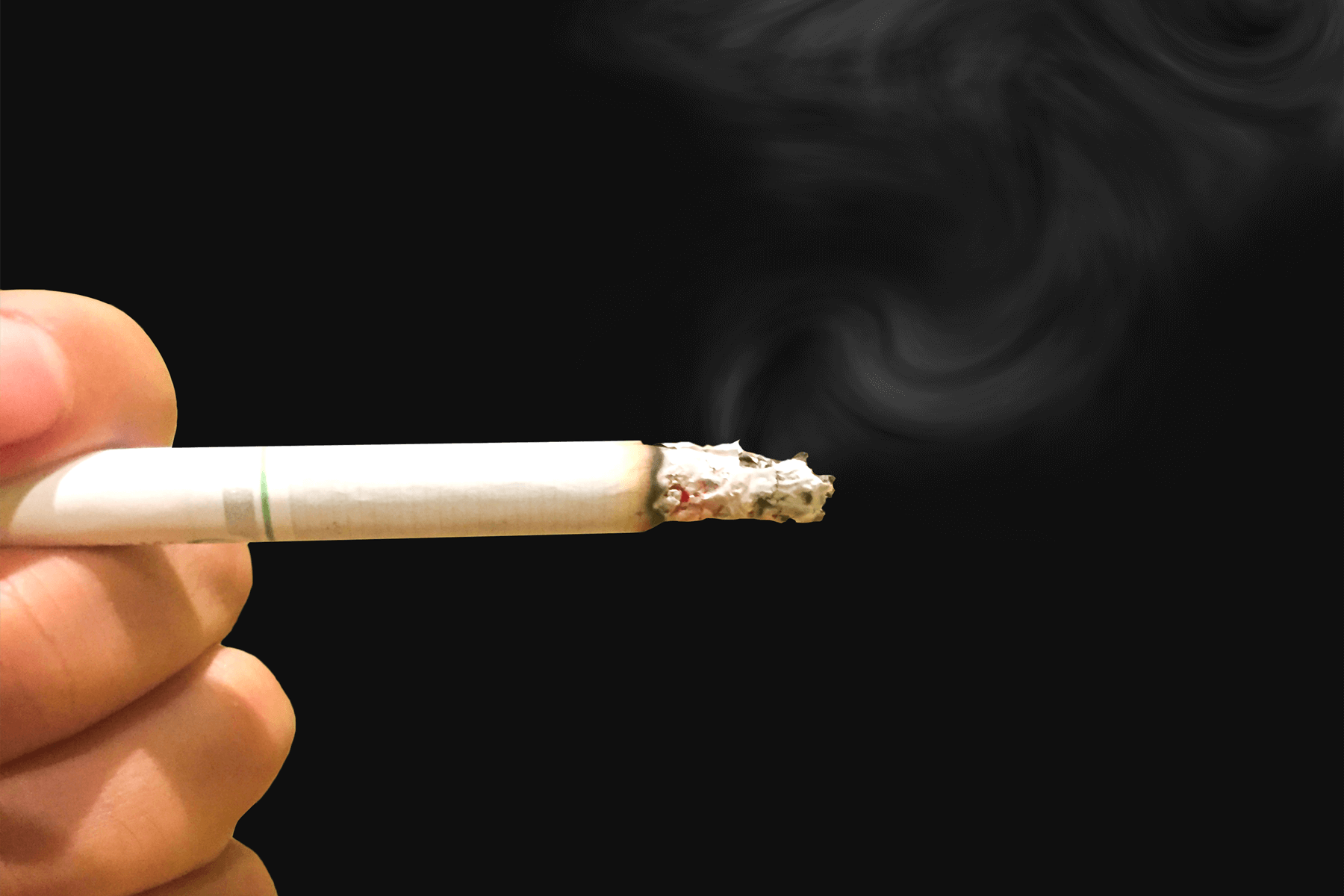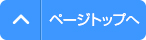飲食店のゴキブリクレーム徹底対策ガイド – 発生原因から予防策・クレーム対応まで
2025.08.29

飲食店でゴキブリクレームが発生すると、店舗の評判や売上に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。ゴキブリクレームを防ぐには、日々の清掃と衛生チェックに加え、専門業者による定期点検でゴキブリの発生を未然に防ぐことが不可欠です。同時に、万が一クレームが発生してしまった場合に備えてクレーム対応マニュアルを整備すること、そして、迅速かつ的確な対応で顧客の信頼回復に努めることが求められます。
本コラムでは、飲食店の経営者や店舗管理者に向けて、ゴキブリ発生の原因や発生した場合のリスク、正しいクレーム対応フローやクレーム後の顧客との信頼回復策について、体系的に解説します。
<目次>
- 飲食店におけるゴキブリクレームの重大性と経営リスク
- 飲食店でゴキブリが発生する主な原因と衛生上の問題
- ゴキブリがもたらす食中毒・異物混入リスクと食品衛生法による行政処分
- ゴキブリクレーム発生時の正しいクレーム対応フロー
- ゴキブリクレーム後の顧客フォローと信頼回復策
- 口コミ・SNSでゴキブリクレームが発信された場合の対処
- 飲食店が日常的に講じるべきゴキブリ予防対策
- ゴキブリクレームを未然に防ぐ衛生管理体制の構築
- サニクリーンのゴキブリ駆除・防除サービス
- 今後のゴキブリクレーム対策における課題と展望 ― 社会的意識の変化と制度的対応の必要性
- まとめ ― 衛生管理は信頼づくりの第一歩、ゴキブリ対策を「強み」に変える視点を
- Q&A|ゴキブリクレームを防ぎたい飲食店経営者のための実践的アドバイス
飲食店におけるゴキブリクレームの重大性と経営リスク

飲食店におけるゴキブリの目撃や料理への混入は、単なる衛生上の問題にとどまらず、深刻な経営リスクを招きかねません。実際に、ある調査では約9割の消費者が「ゴキブリを見た飲食店には二度と行かない」と回答しており、一度の目撃が顧客の強い嫌悪感と不信感を招き、リピーターの喪失に直結することが分かります。
さらに、「不潔」「異物混入」といったネガティブな口コミがSNSやレビューサイトで拡散されれば、新規顧客の来店意欲も大きく損なわれます。株式会社トレタが実施した調査によると、「お店が不潔だった」という口コミを見て来店を控えると回答した人は70.2%にのぼっており、その影響の大きさは明白です。
※参考:悪い口コミ投稿を防ぎ、安心してお店に来てもらうには!アンケート調査結果も紹介
https://toreta.in/contents/dx/ranking005/
加えて、SNS上で一度広まった風評は長期にわたってネット上に残るため、小規模店舗にとっては致命的な打撃となる可能性もあります。また、ゴキブリの発生が保健所へ通報されることで、営業停止命令などの行政処分が下るケースもあります。
このように、飲食店におけるゴキブリクレームは単なるイメージ低下にとどまらず、売上減少、顧客離脱、行政指導といった多方面にわたる経営リスクを伴うものと認識しなければいけません。
飲食店でゴキブリが発生する主な原因と衛生上の問題
飲食店でゴキブリが発生する主な原因は、ゴキブリが好む「高温多湿」「食材くず」「整理されていない環境」が揃っていることです。特に厨房は、熱源、水、食べ物があり、ゴキブリにとって絶好の繁殖環境となります。
床の油汚れ、排水口のぬめり、設備の隙間など、清掃が行き届きにくい場所は、ゴキブリの隠れ家や繁殖の温床になりやすいです。特に、飲食店でよく見られるチャバネゴキブリは繁殖力が非常に強く、「1匹見たら数十匹いる可能性がある」と言われるほど。日常の衛生管理がわずかでも緩んだ瞬間に、爆発的に繁殖することがあります。
このようなゴキブリの繁殖を防ぐためには、ゴキブリの痕跡である「ローチサイン」を見逃さないことが大切です。
▼関連記事
ローチサインとは?飲食店が知っておくべきゴキブリ発生の見分け方と対策
https://www.sanikleen.co.jp/biz/seisou/detail/3371.html
ゴキブリがもたらす食中毒・異物混入リスクと食品衛生法による行政処分

ゴキブリは、下水溝、生ゴミ置き場、トイレなどの不衛生な環境を行き来することで、さまざまな病原性細菌やウイルスを体表および消化器内に保有しています。たとえば、以下のような菌・ウイルスを持っている可能性があります。
・サルモネラ菌
・黄色ブドウ球菌
・大腸菌(O157含む)
・赤痢菌
・ノロウイルス
これらの病原体は、ゴキブリが食材に直接接触したり、器具や調理台の上を歩いたりすることで容易に拡散します。こうしてゴキブリが接触した包丁やまな板、食材に二次感染が広がり、結果として顧客に食中毒を引き起こす事例は後を絶ちません。特にチャバネゴキブリは小型で夜行性のため、閉店後の厨房内で活動しやすく、衛生管理の「死角」になりがちです。
令和4年度、保健所等に寄せられた食品に関する苦情件数は東京都全体で4,071件でした。内訳は「有症(腹痛や嘔吐、発熱など症状や病気が現れている状態)」が最多で1,337件(32.8%)、次いで「異物混入」が565件(13.9%)となっています。異物混入の苦情要因を見ると、ゴキブリ等の「虫」が最も多く、185件(32.7%)、次いで人毛等の「動物性異物」が92件(16.3%)となっています。
※参考:食品衛生責任者・お知らせ版|令和6年6月1日|東京都
https://www.toshoku.or.jp/eiseijigyo/backnumpdf/20240603-200.pdf
提供した料理にゴキブリが混入していた場合、異物混入として食品衛生法違反に問われ、保健所による調査や行政指導、営業停止といった処分を受ける可能性があります。また、上述のとおり、SNSなどでの拡散によって風評被害が広がると、顧客離れやブランド毀損にもつながります。
飲食店は、こうしたリスクを正しく理解し、衛生管理の徹底と法令遵守を行うことが求められます。飲食店は単に駆除を行うだけでなく、ゴキブリの持つ衛生的・法的リスクを正確に理解し、日常の衛生管理を徹底することが重要です。
ゴキブリクレーム発生時の正しいクレーム対応フロー

万が一、提供した料理にゴキブリが混入していた場合、顧客からのクレームは避けられません。ゴキブリによるクレームが発生したとき、飲食店側はどのような対応を取るべきでしょうか。重要な3つのステップを押さえておきましょう。
① 顧客への迅速な謝罪と状況の確認
まず最も重要なのは、現場でゴキブリを目撃した顧客への即時対応です。クレームを申し出た顧客には、店側が真摯に受け止めていることを示すために、誠意を持って謝罪し、「どこで」「どのように」ゴキブリを見たのか、具体的な状況を丁寧にヒアリングします。
この段階では、事実の確認よりも感情への配慮が優先です。否定や言い訳をせず、「ご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪し、適切な補償(返金、代替品、クーポン等)を柔軟に提案します。
重要なのは、顧客に「店が真剣に受け止め、すぐに対処しようとしている」と感じてもらうことです。SNS時代の今、顧客の「感情」「印象」はそのまま投稿に反映されます。即時対応の成否が、後々の風評や炎上リスクに直結するといっても過言ではないでしょう。
② 現場での緊急駆除と衛生状況の応急チェック
顧客対応と並行して、クレームが発生した現場の確認と応急処置を行います。まずは目撃場所にゴキブリがまだ残っているかどうかを確認し、必要であればすみやかに物理的な駆除を行います。殺虫剤や粘着トラップを常備しておくと、緊急時の対応がスムーズです。続いて、以下のポイントを点検しましょう。
・床・排水溝周辺にゴミや油汚れがないか
・食材や調理器具にゴキブリが接触した可能性がないか
・他の客席・厨房で同様の痕跡が見られないか
この一次チェックは、営業を続けてよいかの判断にもつながる重要な作業です。状況によっては、一時的な営業中断や該当席の立入制限も選択肢に入ります。
③ クレーム内容の記録と上長・関係機関への報告
現場対応がひと段落したら、必ず「記録」と「報告」を行います。これは法的リスク管理の観点からも極めて重要です。記録すべき情報には、以下のような項目があります。
・発生日時と場所
・顧客の性別・人数・注文内容(わかる範囲で)
・ゴキブリの出現場所・状況(死骸/生体・移動先など)
・店側の対応内容(謝罪、返金、駆除状況)
・目撃・対応に関わった従業員名
・写真等の証拠
こうした記録は、店舗管理者や本部への報告のほか、保健所からの聴取があった際の説明材料になります。また、店舗マネージャーや衛生責任者は、必要に応じてすみやかに保健所に連絡し、状況説明と衛生点検の要請を行います。保健所への報告は、義務ではありませんが、クレームが大きくなる前に自主的に報告しておくことで、行政指導のプロセスにおいて誠実な対応と評価されるケースもあります。
ゴキブリクレーム後の顧客フォローと信頼回復策
ゴキブリによるクレームは、一度の出来事であっても顧客の信頼を大きく損ないます。だからこそ、現場対応が済んだ後の「フォローアップ」も誠実に行う必要があります。形式的な謝罪だけでは信頼は戻りません。顧客が「この店は本気で改善しようとしている」と実感できる対応が鍵を握ります。
再度の丁寧な謝罪と適切な補償の提案
現場での謝罪とは別に、後日あらためて丁寧な文面による謝罪文やお詫びの電話を行うことで、顧客の印象は大きく変わります。この際、感情的な不満に寄り添いながら、具体的な補償内容を伝えることが重要です。たとえば、次回使える割引券・クーポンの送付などが考えられるでしょう。
これらの補償は、金額の大小よりも「誠意」が問われます。顧客が「クレームを大切に扱ってもらえた」と感じることで、飲食店としての信頼を少しずつ取り戻すことが可能になります。
害虫発生の原因究明と改善策の実施報告で安心感を与える
ゴキブリクレームが発生した飲食店が信頼を回復するためには、「なぜゴキブリが発生したのか」「今後どう防ぐのか」を明確にし、それを顧客にしっかり伝える必要があります。これは一種のリスク説明責任(アカウンタビリティ)であり、透明性の高い対応が顧客の安心感を育みます。たとえば、以下のような対策を伝えると効果的です。
・駆除業者による再点検と殺虫処理の実施
・厨房内の清掃体制の強化(写真や記録があれば提示)
・ゴミ置き場や排水設備の管理体制の見直し
・HACCPに準拠した衛生管理手順の再徹底
顧客からのクレームは、内部改善のきっかけになる貴重な機会でもあります。その旨を正直に伝えることで、顧客側も「店側があの件をなかったことにしていない」「顧客の声を大切にしている」と感じ、信頼回復への道が拓けます。
口コミ・SNSでゴキブリクレームが発信された場合の対処

飲食店で顧客がゴキブリを目にした場合、現場ではクレームにならなくても、後日、口コミサイトやSNS上にクレームが投稿されるケースもあります。ゴキブリクレームが拡散されることで、新規顧客の来店意欲を削ぐだけでなく、店舗ブランドそのものへの信頼が損なわれる可能性があります。飲食店としては、以下のような対応を行いましょう。
ネガティブ口コミへの誠実な返信と謝罪・改善策の説明
Googleマップや食べログなどに、「店内でゴキブリを見た」「料理にゴキブリが入っていた」といった口コミが投稿されている場合、他の閲覧者に与える影響は非常に大きくなります。このような投稿には、以下のような方針で返信を行うことが望ましいです。
・経緯や投稿内容を否定せず、まずは真摯な謝罪を行う
・事実確認および対応内容を簡潔に伝える
・今後の改善策や再発防止への取り組みを明記する
ポイントは、投稿者本人だけでなく、他の閲覧者に対する誠意と信頼感を示すことです。攻撃的・反論的な返信は、二次炎上の火種になるため厳禁です。
SNS上で拡散された場合の迅速な公式アナウンス対応
Twitter(現X)やInstagram、TikTokなどのSNS上にゴキブリ目撃情報が写真や動画付きで拡散された場合、対応のスピードと正確性が極めて重要になります。店舗管理者・本部は即座に情報の正確性を確認し、必要に応じて公式アカウントを通じて説明と謝罪を発信します。この際、以下のような情報を含めると効果的です。
・顛末の説明(時系列と発生場所)
・目撃や投稿に対する真摯な謝罪
・現在の対応状況と再発防止策の表明
・問い合わせ窓口の案内(DMや電話番号)
事実に基づいた情報を、過不足なく、感情を抑えた文体で投稿することが大切です。
飲食店が日常的に講じるべきゴキブリ予防対策
飲食店がゴキブリによるクレームを防ぐには、「発生してから対応する」のではなく、「日頃から予防しておく」ことが最も大切です。日常的に取り組むべき具体的な予防策を3つの観点からご紹介します。
厨房・店内清掃の徹底と衛生管理チェックリストの活用
ゴキブリは「暗所」「湿気」「食品残渣」を好みます。特に厨房まわりは熱源や水分が集中するため、床の隅や冷蔵庫下、排水口まわりなどの「死角」の清掃を徹底することが重要です。そのためには、「気づいたときに掃除する」のではなく、清掃箇所を明文化したチェックリストを作成し、記録・管理することが効果的です。以下は、チェックリストの例です。
・コンロ・シンク・作業台の下をモップ清掃(毎日)
・冷蔵庫・冷凍庫の背面や下部を確認・拭き取り(週1回)
・排水口のトラップとフタを外して洗浄(週2回)
・ごみ置き場とその周辺の除菌と乾燥状態チェック(毎日)
こうした清掃習慣の積み重ねが、ゴキブリの「巣」になる場所をつくらない環境づくりにつながります。
ゴキブリの侵入経路封鎖(隙間の充填・網戸設置など設備対策)
外部からのゴキブリの侵入を防ぐには、「物理的な遮断」が効果的です。ゴキブリは1.5mm程度の隙間があれば侵入できるといわれており、飲食店の設備まわりには意外な盲点が数多くあります。たとえば、以下のような対策で侵入経路を封鎖しましょう。
・厨房の排水管や配線の穴、換気扇まわりの隙間をパテやコーキング材で封鎖
・出入口のドアの下部に隙間風防止ブラシ(ドラフトストッパー)を設置
・窓のある店舗では防虫網戸を導入し、開閉時の虫の侵入を防ぐ
・ごみ置き場にはフタ付きゴミ箱と密閉性の高いコンテナを使用し、臭いの拡散と虫の誘引を抑える
このように侵入経路を物理的に遮断することは、発生源の根絶と並んで重要な対策です。
定期的な害虫駆除業者の導入とモニタリング(トラップ設置等)
飲食店のゴキブリクレームを半永久的にゼロにするためには、専門業者による点検・対策が欠かせません。多くの専門業者は月に1〜2回のペースで、ベイト剤(毒餌)の設置、隙間の封鎖、モニタリング用トラップ(フェロモントラップなど)の点検を行います。これにより、「ゴキブリが出る前に兆候をつかむ」という予防型の管理体制が実現します。
▼関連記事
飲食店のゴキブリ対策の正解|効果的なサービスも紹介
https://www.sanikleen.co.jp/biz/seisou/detail/3320.html
ゴキブリクレームを未然に防ぐ衛生管理体制の構築
ゴキブリの目撃や混入といったクレームは、単発の清掃不備や個人の不注意だけで起こるものではありません。多くの場合、飲食店全体の「衛生管理体制の弱さ」が根本原因になっています。つまり、組織的なルール・教育・役割分担ができていないことが、ゴキブリクレームを招くということです。こうした事態を防ぐには、飲食店全体で予防的な衛生管理を仕組み化することが不可欠です。以下にその具体策を示します。
クレーム対応マニュアルの整備とスタッフ間の共有
どんなに清掃や駆除に力を入れていても、「もしものとき」に備えた対応マニュアルがなければ、現場は必ず混乱します。特にゴキブリなどの異物クレームは、接客・衛生・広報の要素が絡むため、スタッフ個人に判断では対応が一貫せず、クレームが深刻化してしまうケースもあります。そうならないようにするには、以下のような項目を盛り込んだゴキブリクレーム対応マニュアルの整備をおすすめします。
・ゴキブリを発見した顧客への初期対応フレーズ
・謝罪のタイミングと補償提案の基準
・店舗管理者へのエスカレーションルート
・保健所・本部への報告フロー
・SNS投稿や口コミ拡散が確認された場合の広報手順
定期的な衛生管理研修とクレーム対応シミュレーションの実施
ルールを作るだけでなく、実際にスタッフがそのルールに基づいて動けるかを確認・訓練する機会を設けることも大切です。衛生対策やクレーム対応の知識は、教科書で学んでも現場で発揮できるとは限りません。だからこそ、定期的な研修とシミュレーションが重要になります。研修では、たとえば以下のような内容を取り入れると効果的です。
・ゴキブリの発生原因・媒介菌・健康被害の基礎知識
・清掃のコツ(死角の見つけ方、洗剤の使い分けなど)
・過去に実際に起きた異物混入・炎上事例の共有
・クレーム時のロールプレイング(例:料理に虫が入っていたと言われたら?)
特に新人スタッフは、ゴキブリという生理的嫌悪を伴うクレームに対してパニックになりやすいため、冷静に対応できるようにするための訓練が不可欠です。スタッフ全員が同じレベルで衛生管理ができ、同じレベルでクレーム対応ができる状態が理想です。
衛生責任者の配置と役割明確化による管理レベル向上
衛生責任者がいない飲食店では、ゴキブリクレームの発生時に「誰が対応するのか」が不明確になり、再発も起こりやすくなります。衛生管理体制を形骸化させないようにするには、専任または兼任の「衛生責任者」を配置することが重要です。飲食店において衛生責任者は次のような役割を果たします。
・衛生チェックリストの運用・記録管理
・害虫の目撃・発見の報告受付と初動対応
・清掃や衛生用品の在庫管理・補充
・駆除業者や保健所との連絡窓口
・他スタッフへの衛生教育と改善提案
このように責任体制を明確にすることで、「衛生管理は全員でやるが、最終責任はこの人が持つ」という意識が現場全体に浸透し、属人化しない仕組みとしての衛生管理が可能になります。
▼関連記事
飲食店のゴキブリ対策の正解|効果的なサービスも紹介
https://www.sanikleen.co.jp/biz/seisou/detail/3320.html
サニクリーンのゴキブリ駆除・防除サービス
ゴキブリに関するクレームが寄せられるなど、ゴキブリ発生・繁殖のリスクを感じている飲食店におすすめしたいのが、サニクリーンの「ゴキブリ駆除・防除サービス」です。
ベイト剤方式を採用し、ゴキブリの習性を利用して巣ごと根絶。再発を防ぐ年間管理プログラムで、良好な衛生環境を持続できます。店舗の営業時間中でも施工でき、準備や片付けも不要。少量のベイト剤で最大限の効果を発揮できるよう施工するので、まわりの環境や人体に影響を及ぼす心配はありません。地下の店舗やテナントが密集したビルなど、換気が万全でないところや締め切った空間でも安心です。
サニクリーンでは、無料にて現地調査を承っております。現地調査では、ゴキブリの生態や習性を熟知したプロが、生息箇所や繁殖状況をくまなく確認してご報告を差し上げます。ゴキブリのローチサインが気になる方は、まずは現地調査で生息状況を把握することから始めましょう。
今後のゴキブリクレーム対策における課題と展望 ― 社会的意識の変化と制度的対応の必要性
近年はSNSの発展により、過去には表面化しなかったような衛生トラブルも一気に拡散・可視化される時代となりました。ゴキブリの目撃や料理への混入に対するクレームが拡散すれば、飲食店としての信頼は瞬く間に失われてしまいます。
今後は、単なる衛生対策だけでなく、「クレーム後の透明性ある対応」「誤情報への冷静な広報」といった情報対応力も、飲食店の評価を左右する重要な要素となるでしょう。
さらに、消費者側も、衛生に対する関心の高まりと同時に、「許容範囲の低下」という傾向が見られます。これは裏を返せば、誠実な対応を行えば信頼を取り戻せる可能性があるということです。これからの飲食店は、「ゼロリスク」を目指すだけでなく、リスク発生時にどう信頼を再構築するかという視点を持つことも重要になってくるでしょう。飲食店経営者や衛生担当者にとっては、こうした時代背景を踏まえた「予防と対応の両立」こそが、今後の持続的な店舗運営の鍵になるはずです。
まとめ ― 衛生管理は信頼づくりの第一歩、ゴキブリ対策を「強み」に変える視点を
ゴキブリによるクレームは、飲食店にとって非常に大きなリスクである一方で、日々の予防と体制整備によって確実に減らせる問題でもあります。クレームの発生を「偶発的なトラブル」と捉えるのではなく、飲食店としての運営レベルや顧客への誠意を示す「試金石」と考えることで、より前向きな改善と信頼構築につながります。
本コラムで紹介した各対策は、いずれも特別な技術や高額な設備を必要とするものではなく、今日からでも着手できるものばかりです。衛生管理を「コスト」ではなく「信用資産」と捉え、スタッフとともに取り組むことで、ゴキブリ対策は飲食店としての強みへと変わります。
クレームのない飲食店ではなく、クレームに誠実に対応し、再発を防ぐ努力を継続できる飲食店こそが、長く愛される飲食店です。強固な衛生管理体制を構築するとともに、万が一のクレームに対する迅速かつ誠実な対応力を磨くことで、安心と信頼に満ちた食の提供を目指しましょう。
Q&A|ゴキブリクレームを防ぎたい飲食店経営者のための実践的アドバイス
Q.1 ゴキブリクレームがあった後、営業を続けても問題ないですか?
A. 衛生状況を即時に確認し、問題がなければ営業継続は可能です。
ただし、顧客の目撃証言や現場状況から、厨房や食材にゴキブリが接触した可能性がある場合は、一時的に営業を中断して衛生確認・応急処置を行うべきです。自主的な中断と誠意ある説明が、むしろ顧客の信頼回復につながることもあります。
Q.2 ゴキブリ駆除に市販の殺虫剤を使っても大丈夫ですか?
A. 一時的な対応としては可能ですが、根本的な解決にはなりません。
市販のスプレー型殺虫剤は目に見える個体への応急対応には有効ですが、卵や巣、侵入経路には効果がありません。継続的な予防や再発防止には、ベイト剤の設置やプロによる処理・点検が欠かせません。
Q.3 ゴキブリが1匹でも出たらHACCP違反になりますか?
A. 直ちに違反と判断されるわけではありませんが、管理体制が問われます。
HACCPは異常発生時の対応手順を含めた管理体系です。1匹のゴキブリが出ただけで即違反にはなりませんが、「発生後の対応が適切かどうか」が評価の対象となります。発生原因の特定と対策が不可欠です。
Q.4 ゴキブリ発生は季節によって変化しますか?
A. はい、特に夏場にかけて活発になります。
ゴキブリは高温多湿を好むため、6月〜9月の梅雨〜夏季にかけて繁殖と活動が活発になります。そのため、4月〜5月のうちに清掃強化・設備チェック・業者点検を実施しておくことで、ピーク時の発生を抑えやすくなります。
Q.5 異物混入の中でも、ゴキブリは特に問題になりますか?
A. はい、心理的影響が大きく、クレームや炎上につながりやすいです。
毛髪や紙片などと比較して、ゴキブリは「不衛生」「病原菌」「見た目の嫌悪感」など、多重のリスクを持つ異物です。実際、SNSやレビューでも炎上しやすく、保健所への通報件数も多いため、飲食店にとって特に注意が必要な異物だといえます。
Q.6 ゴキブリの目撃が複数回あった場合、営業停止になる可能性はありますか?
A. 状況によっては営業停止などの行政処分につながる可能性があります。
複数回の目撃や顧客クレームが続き、改善が見られないと保健所からの衛生指導にとどまらず、営業停止や改善命令が出ることもあります。過去には異物混入を軽視した店舗が、営業許可取り消し処分を受けた事例もあります。初期段階から迅速な対応が重要です。
Q.7 店舗が古く、隙間や設備の老朽化が気になります。どう対処すべきですか?
A. 優先順位を決めて段階的に修繕・補強しましょう。
すべてを一度に改修するのは難しくても、まずは「侵入経路になりやすい場所」から順に隙間を塞ぎ、通気口や排水まわりの防虫対策を講じましょう。専門業者の診断を受ければ、費用対効果の高いポイントから対応できます。
Q.8 ゴキブリが1匹も出ていなくても、業者に依頼する意味はありますか?
A. はい、予防目的でも業者依頼は非常に有効です。
プロは目に見えない兆候や発生リスクを察知できます。たとえば排水口のにおいやフンの痕跡など、見落としがちなポイントも確認され、未然に防ぐことが可能です。定期点検契約は、クレーム防止の「保険」ともいえる存在です。
Q.9 ゴキブリを理由に低評価レビューを書かれたら、削除できますか?
A. 内容次第では削除申請が可能ですが、原則としては難しいです。
事実に基づく内容であれば、レビューサイトは投稿を削除しないことが多いです。ただし、虚偽や誹謗中傷が含まれる場合には、運営元に対して適切な削除依頼ができます。いずれにせよ、誠実な返信で印象の緩和を図る方が現実的です。
Q.10 清掃や駆除対策をしてもゴキブリが出てしまうのはなぜですか?
A. 店舗の立地環境や近隣状況も大きく影響します。
ビル全体の衛生状態が悪い、隣接テナントが管理を怠っているなど、個店の努力だけでは防ぎきれないケースもあります。こうした場合はビル管理会社や他店舗と連携し、建物全体で防虫対策を講じることが求められます。
<参考文献>
※参考:ゴキブリ|公益社団法人東京都ペストコントロール協会
https://www.pestcontrol-tokyo.jp/img/pub/panph04.pdf
※参考:ゴキブリを知る|害虫を知る|アース害虫駆除なんでも事典
https://www.earth.jp/gaichu/knowledge/gokiburi/index.html