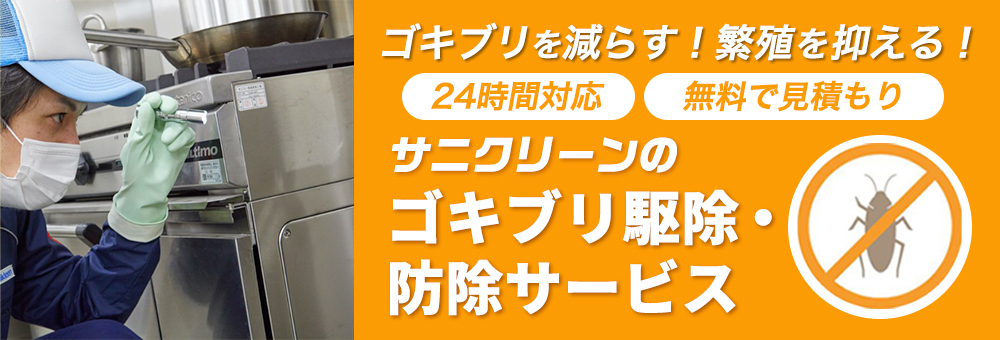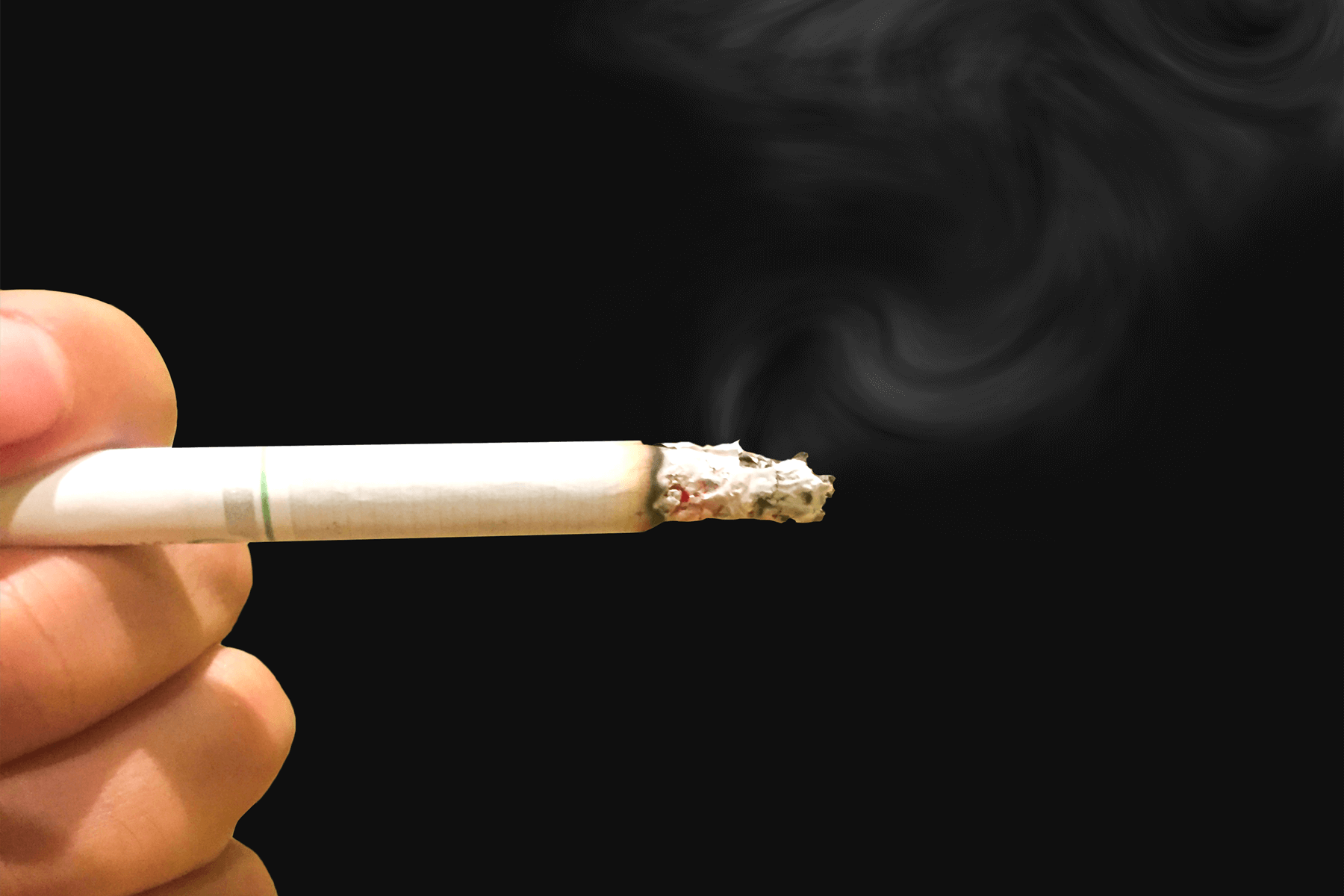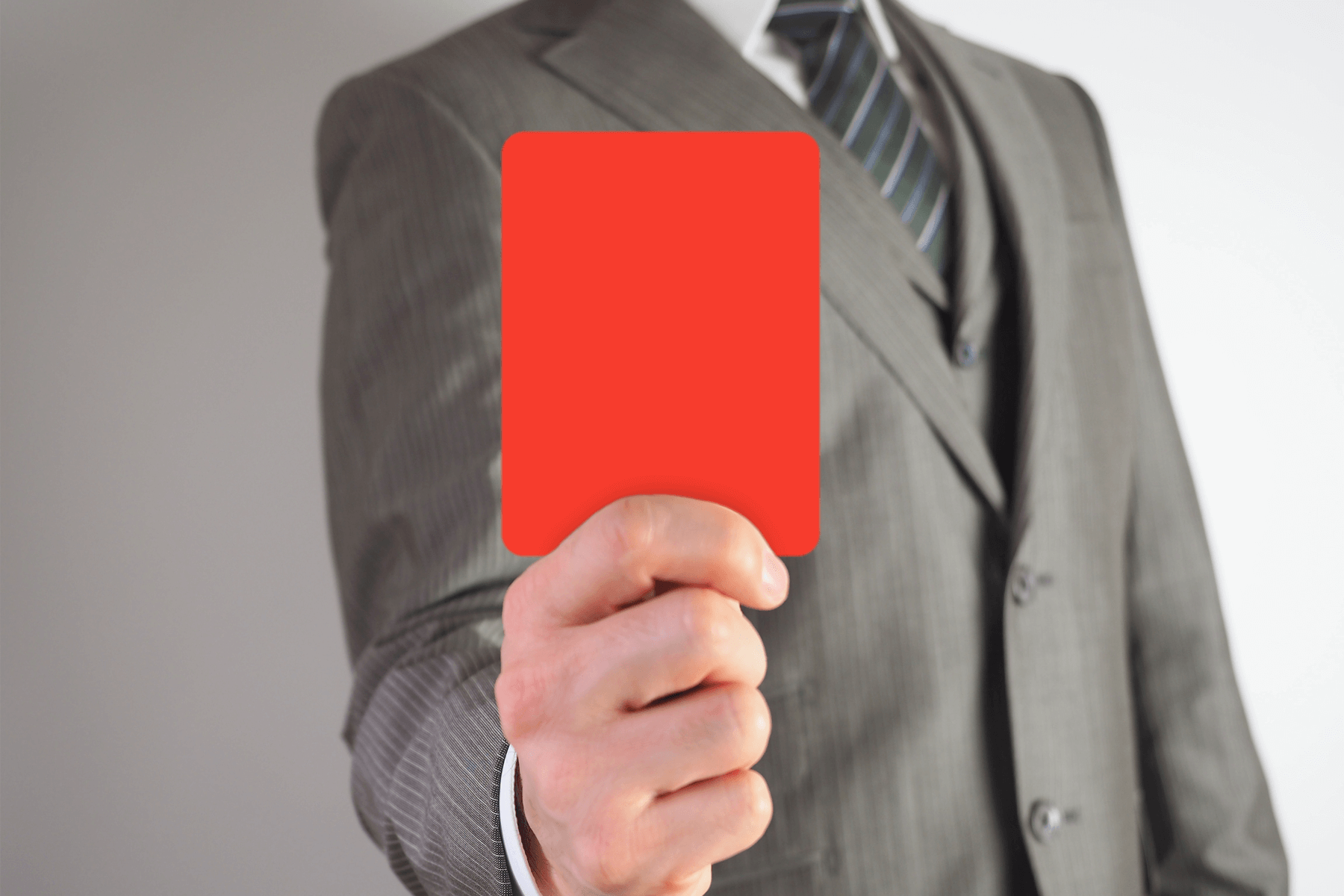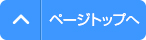梅雨に多発する食中毒を防止せよ…
飲食店の「異物混入」対策|虫や毛髪など発生原因も紹介
2025.04.10

飲食店の異物混入原因は多岐にわたり、従業員の身だしなみの不備、調理器具の破損、ハエやゴキブリなどの害虫の混入などがあげられます。対策としては、主に、異物混入リスクに関する従業員の危機意識を向上させる「教育」と、「環境整備」の2つとなります。教育では従業員全員が対策を共有できるマニュアルの作成もポイントになります。
また、お客様のクレームに備えることも大切で、経営リスクを下げる重要な対策となります。

<コラムをすべて読む時間がない方(いますぐ異物混入を防ぎたい方)>
虫や髪の毛、異物混入のリスクを無料で見える化する「サニクリーンの異物混入の無料調査・改善アドバイス」をご覧ください。
<目次>
飲食店で異物混入が発生してしまう原因と対策方法

料理への異物混入は、お客様に健康被害をもたらす恐れがあります。また、対応によっては「客離れ」を招くこともあり、経営的なリスクが高まります。また、法的な責任問題に発展する、営業停止処分を受けるなど、異物混入によるダメージは枚挙にいとまがありません。そこで、飲食店としては、しっかりとした備えが必要になります。
異物が混入する原因は、主に以下の2つに分類されます。
(1)従業員(店舗側)の危機意識が低いこと
(2)異物が混入する環境になっていること
まずは、「従業員(店舗側)の危機意識が低いこと」については、従業員への教育(指導)の徹底が基本対策になります。
制服やアクセサリーなどの身だしなみのチェックをはじめ、自分が異物を生み出す存在であることを認識してもらった上で、混入の原因となるものを外すなどの対策を施します。
また、「異物が混入する環境になっていること」については、調理する近くに余計なものは置かない(「調味料と間違える可能性があるため、洗剤を近くに置かない」など)、容器には内容物の名前を書いて誤った使用を防止する、厨房などを明るくし、異物混入を気づきやすくするなどの対策を施します。
飲食店における主な混入物
代表的な異物には、毛髪やアクセサリーなどの従業員が身につけているもの、調理器具や食器の破片、ハエやゴキブリなどがあげられます。
そこで、ここでは飲食店で混入リスクが高い異物を紹介します。
毛髪
毛髪の混入は非常に一般的です。主に、調理中の従業員の毛髪が調理中に料理に落ちることで発生します。また、ホールスタッフの毛髪が入ることもあります。毛髪の落下対策には厨房スタッフはもとより、ホールスタッフも帽子をかぶることが効果的です。
アクセサリーなど、スタッフが身につけているもの
ジュエリーやアクセサリー(指輪やイヤリング、ピアスなど)、従業員が身につけている物が調理中に食品に混入することがあります。就業中はアクセサリーなどを外しましょう。
また、アクセサリーではありませんが「つけ爪」にも注意しましょう。
ばんそうこう
手のケガによる「ばんそうこう」も混入リスクが高い異物となります。ただし、ケガを治療しているものなので、はずすわけにはいかないという場合も多いと思います。その場合は、手袋をしてばんそうこうが落下しないようにします。
また、そもそも、ばんそうこうを付けた手(素手)で食品や料理を扱うのは「食中毒のリスク」を高めます、そのような意味でも手袋はしっかりするように指導しましょう。
制服の生地、ボタン
制服(ユニフォーム)の生地ほつれや、ボタンなども原因としてあげられます。ユニフォームもしっかりとした管理が必要です。
調理器具、食器など
調理器具や食器の破損、劣化により、小さな破片が料理に混入することがあります。定期的な器具や食器の点検と交換が必要です。中には、ガラスや金属片など、危険度が高いものもあるためしっかりと予防策を講じましょう。
また、調理時に出る「紙」や「ラップ」などが混入する恐れもあるため注意が必要です。
洗剤など
容器が似ている、ラベルがないので内容物がわからない、間違えやすいところに置いてあるなどが原因で、洗剤などを調味料と間違えて、調理に使用してしまうことがあります。
虫(ハエやゴキブリなどの害虫)
ハエやゴキブリなどの害虫は特に夏場に多く、食材の保管方法や厨房の衛生状態によっては店内に繁殖し、料理に混入することがあります。食材を適切に保管するとともに、厨房を中心とした衛生管理を定期的に行いましょう。
仕入れた「加工食品」に異物が混入している
カット野菜や煮豆など、既に加工されている食品(食材)を購入されているお店も多いかと思います。その場合、袋や缶詰などから出してそのまま提供するのではなく、異物が入っていないかを検査することが重要です。
加工段階で、異物が混入してしまっている可能性もあるため、常に検査を怠らないようにしましょう。
10件に1件は異物混入による苦情が寄せられている

令和4年、都内(東京都、特別区、八王子市及び町田市)の食品に関する苦情件数をみると、最も多い苦情が「異物混入」でした。その割合は13.9%と、10件に1件という高い割合で発生しています。
異物混入が飲食店にとって高いリスクであることが想像できます。
| 要因分類 | 件数 | 構成比(%) |
| 合計 | 4,071 | 100.0 |
| 異物混入 | 565 | 13.9 |
| 腐敗・変敗 | 75 | 1.8 |
| カビの発生 | 53 | 1.3 |
| 異味・異臭 | 145 | 3.6 |
| 変色 | 20 | 0.5 |
| 変質 | 16 | 0.4 |
| 食品・器具の取扱い | 515 | 12.7 |
| 従事者 | 193 | 4.7 |
| 表示 | 257 | 6.3 |
| 有症 | 1,337 | 32.8 |
| 施設・設備 | 475 | 11.7 |
| その他 | 420 | 10.3 |
令和4年度 要因別苦情件数
【引用】東京都保険医療局
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin//kujou/index.html
飲食店において異物混入を発生させないための具体的な対策

飲食店での異物混入を未然に防ぐためには、いくつかの具体的な対策が必要です。
身だしなみの管理
・毛髪の落下対策には厨房スタッフはもとより、ホールスタッフも帽子をかぶるようにします。
・指輪やイヤリング、ピアスなどのアクセサリーや「つけ爪」も外します。
・手をケガし「ばんそうこう」をしている場合は、手袋をしてばんそうこうが落下しないようにします。
※ばんそうこうを付けた手(素手)は「食中毒のリスク」を高めるため、できれば調理業務の中止をお勧めします。
制服(ユニフォーム)の管理
先ほども紹介したようにユニフォームの生地ほつれや、ボタンなども異物混入の原因としてあげられます。ユニフォームの衛生管理も兼ね、メンテナンス管理を外注するのも効果的な対策のひとつです。
また、ユニフォームはボタンがない、もしくは外側についていないものを選ぶとよいでしょう。
調理器具、食器などの管理
使用する調理器具や食器が破損、劣化している場合は速やかに交換します。特に、金属疲労や破損が見られる器具は、直ちに新しいものに換えましょう。
洗剤・備品などの管理(置き場所の注意)
先ほども紹介した通り、容器が似ている、容器にラベルがないので内容物がわからない、間違えやすいところに置いてあるなどが原因で、洗剤などを調味料と間違えて、調理に使用してしまうことがあります。そこで、厨房内で使用する洗剤や備品、器具の保管場所・方法にも注意が必要です。
<事例> 「界面活性剤混入の酒だれによる食中毒」
ある飲食店でお客様が異物混入による舌のしびれを訴えた事件が発生しました。原因は、調味料として提供されたはずの「酒だれ」の容器に誤って「廃油処理剤」が入れられていたためです。
調査により、容器の類似性と新人アルバイトのミスが事故の要因とされました。対策として、調味料の容器を明確に区別し、新人研修を徹底することが求められました。
(参考)東京都保険医療局
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/foods_archives/foodborne/operators/index.html
グリストラップなど、害虫の発生個所を清潔にする
グリストラップ(またはグリーストラップ)の衛生管理は、飲食店で非常に重要です。
グリストラップはハエやゴキブリなどの害虫が発生しやすい場所のひとつです。そこで、グリストラップを定期的に清掃することで、虫の発生自体を抑えます。また、排水溝やゴミ箱など、虫が集まりやすい場所の衛生管理は徹底して行いましょう。
食材受け入れ時の対策を徹底
加工食材を含め、野菜などの食材が店舗に納品された際には、しっかり異物検査をするようにしましょう。また、日頃から、信頼できる納入業者とお付き合いし、高い品質基準を設けておくことも有効な対策です。
厨房を明るくし、異物を発見しやすくする
間接照明などで客席がうす暗いお店もありますが、厨房や料理を受け取るカウンター周りなどは明るくしておきましょう。異物など、料理に異常があれば気づきやすくなります。
視力が低い人はメガネやコンタクトをして異物を発見しやすくする
調理の際、視力が低いと異物が混入した(または、している)ことに気づけない場合があります。そこで、視力に応じてメガネやコンタクトレンズを装着するようにしましょう。
最も異物混入が起きやすい場所を決めておく
厨房内で、最も異物混入のリスクが高い場所を特定します。この場所では特に高い衛生基準を設け、定期的に清掃などの衛生管理を行うようにしましょう。
最も重要なのは従業員の意識

ここまで原因と具体的な対策を紹介してきましたが、最も大切なことは、異物混入リスクに対する「従業員の意識」です。
身だしなみも、食材の管理も、掃除も、すべて従業員の意識があって効果的に具体化される対策です。そのため、経営者(管理)側は、従業員に対して教育を施す必要があります。具体的な事例の共有、視覚的な教材を用いたトレーニング、定期的な評価とフィードバックをくり返すことで、異物混入のリスクは確実に低くなります。
また、異物混入リスクを防ぐためには、従業員全員が統一した行動を取ることも不可欠です。そのため、対策を記した「マニュアル」の作成をおすすめします。そしてマニュアルは従業員がいつでも読める状態にしておきましょう。また、定期的に見直しを図り、リスク管理の質を高めていきます。
ゴキブリの混入は数えきれないダメージを経営に与える
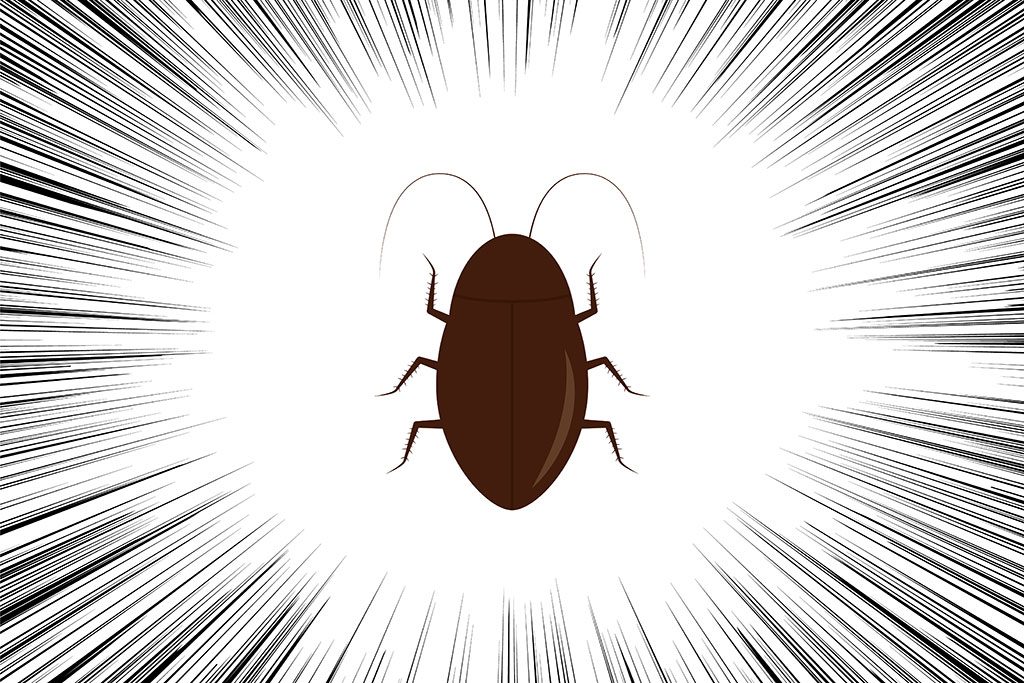
害虫の異物混入に関するニュースを耳にすることがあると思います。中でもゴキブリの混入が確認されると、社会的なインパクトが大きく、数えきれないほどのダメージを経営に与えます。
そこで、次からは、ゴキブリに焦点をしぼった飲食店での対策を紹介します。また、飲食店のゴキブリ対策はハエなどの害虫、ネズミなどの害獣対策にも一定の効果がみられます。
清掃・整理整頓
毎日の徹底した清掃と整理整頓は、ゴキブリの繁殖を防ぐため最も基本的、且つ効果的な対策です。特に、厨房や倉庫、排水口など、食べ物の残りや水分が溜まりやすい場所を重点的に清掃しましょう。冷蔵庫などの厨房機器の下や裏などもできれば清掃したいポイントです。
また、整理整頓をすることで、ゴキブリの隠れ場所を減らすことができます。
ベイト剤の使用
ベイト剤はジェル状の毒エサで、ゴキブリ対策に非常に効果的です。
ゴキブリが頻繁に出没する箇所や通り道に設置することで、長期間にわたって効果を発揮します。このベイト剤を摂取したゴキブリが巣に戻って死ぬと、その死骸を他のゴキブリが食べることで連鎖的に駆除が進むため、ゴキブリの繁殖を長期的に抑えることができます。
しかし、この方法にはしっかりとした管理が必要です。先ほども紹介しましたが、定期的に観察を行い、設置場所や効果を確認し、適切に改善を行うことで、持続的な効果を維持する必要があります。そのため、管理に手間がかかるというデメリットがあります。
ゴミ対策
飲食店でのゴキブリ対策において、「ゴミ」の適切な処理は非常に重要です。
ゴキブリは、食べ物のカスや生ゴミを主なエサにして繁殖するため、ゴミの管理を徹底することが大切です。
以下にゴミ処理のポイントを紹介します。
1.毎日のゴミ捨てを徹底する
ゴミは毎日必ず処理し、店内に長時間放置しないようにします。特に生ゴミは、ゴキブリのエサになりやすいため、こまめに捨てましょう。
2.フタ付きのゴミ箱を使用する
ゴミ箱には必ずフタをし、ゴキブリが侵入できないようにすることが重要です。開いたゴミ箱や不十分な密閉状態のゴミ箱は、ゴキブリの格好のエサ場となる可能性があります。
3.ゴミ箱周辺の清掃を徹底する
ゴミ箱の周囲にも食べ物のカスが散らかることが多いので、定期的にゴミ箱周辺を清掃し、ゴキブリのエサとなるものを残さないようにしましょう。
4.排水溝やシンク周りのゴミ除去
ゴミや食べ物のカスが排水溝にたまると、ゴキブリが発生しやすくなります。排水溝やシンク周りのゴミは定期的に取り除き、衛生状態を保つことが大切です。
段ボール対策
食材などが入った段ボールの断面のすき間にはチャバネゴキブリがいる可能性があります。ゴキブリが店内に持ち込まれる原因のひとつになるので、そのまま店内に放置するのはやめましょう。
また、既に店内にいるゴキブリにとっては、格好にすみ家(産卵場所)になってしまうことがあります。
食材の保管対策
食材は外に置かず、なるべく冷蔵庫やフタのついたケースに保管するようにしましょう。
窓や排水管のすき間対策
ゴキブリは小さなすき間からも侵入します。窓や排水管、配管用のスリーブ周辺にすき間があれば、シリコンやパテで埋めます。外部からのゴキブリの侵入を防ぐ対策となります。
忌避剤の設置と換気対策
ゴキブリが嫌うハーブ成分を含んだ忌避剤を設置するともに、店舗内の湿気上昇によるゴキブリの活動を抑えるため、換気をしっかり行い湿度を管理することも大切です。
飲食店のゴキブリ対策の正解
ゴキブリの繁殖を抑える対策の正解は「防除」です。
ゴキブリがすでに店内で繁殖してしまった場合には、殺虫剤の噴霧などによる「駆除」で数を減らします。ただし、駆除だけでは、繁殖しやすい環境を改善してないこと、殺虫剤で死なない卵が残り孵化することなどが原因で、再び繁殖する恐れがあります。
防除とは、ゴキブリの繁殖を防ぐために継続的に行う対策のことで、日常的な管理が基本となりますが、時間と手間がかかるのがデメリットです。そのため、専門業者へ依頼することも検討しましょう。
異物混入時のお客様への対応(クレーム対応)

異物混入に対するクレームには、迅速かつ適切な対応が欠かせません。迅速、適切は、お客さまの信頼を回復し、ネガティブな影響を最小限に抑えるためには極めて重要です。そこで、クレームに対する基本的な対応を紹介します。
クレームに対応する人は店長クラスが適切
クレームが発生した場合、アルバイトなどのスタッフではなく、店長などの責任者クラスが対応しましょう。責任者が対応することで真摯な態度が伝わります。
お客様の話をよく“聴く”
お客様が話している最中は話を遮らずに最後まで耳を傾けます。お客様の話を“聴く”姿勢に加え、時間をかけて冷静になるまで待つことが、これ以降の建設的な対話を可能にします。
また、否定をしてはいけません。事実である場合はそれを認め、対応を進めることが大切です。ただし、事実をしっかり確認する必要はあります。お客様の勘違いや、場合によっては嫌がらせということもあります。その場合の対応も、事前に決めておく必要があります。
お詫びの仕方
お詫びの仕方と、どのような形でお詫びをするかをあらかじめ決めておきます。例えば、料理を無料にする、割引クーポンを渡す、追加サービスを提供するなど、お客様が納得する形でお詫びをしましょう。
必ず原因を確認し改善に努める
お客様へのクレーム対応だけではなく、異物混入が確認された場合は原因を確認し、再発防止に努めましょう。どのような異物がどの料理に含まれていたのか、異物が発見された状況など、従業員全員で事例や原因を共有し、対策を確認しあうことが重要です。
第三者(専門業者)による定期的な調査が有効
異物混入を防ぐためには、お店側での定期的なチェックと改善に加え、第三者(専門業者)による定期的な調査(評価)を受けることで、大きくリスクが低減します。
専門業者から客観的な評価を得ることで、見落とされがちな問題点を発見し、より効果的な改善策を講じることができます。
第三者評価はお店の評価を高める
第三者評価を定期的に受けることは、お店の安全基準の高さを示していることになるため、お客様からのポジティブな評価を高めます。お店のホームページやSNSで、積極的にアピールしていきましょう。
サニクリーンの「異物混入の無料調査・改善アドバイス」サービス

サニクリーンの「異物混入の無料調査・改善アドバイス」は、飲食店などの食品事業者向けに特化したサービスで、異物混入のリスクを現場で評価し、具体的な改善策を提案します。
異物混入リスクを減らし、食品安全を強化したい店舗様にとっておすすめの「無料サービス」です。
<異物混入の無料調査・改善アドバイスの主な特徴>
- 徹底した現地調査
専門家が直接店舗に訪問し、異物混入のリスク(場所・状況・行動など)を洗い出します。 - 改善提案
店舗の状況を詳細に分析し、リスクを減らすための具体的な改善策を提案します。 - 全国対応
一部島しょ部などを除き、47都道府県対応可能です。 - 従業員教育(無料)
サービスを利用された企業様限定で、従業員の衛生意識向上のための「無料講習会」を提供します。
※地域、時期により提供していないことがあります。事前にお問い合わせください。
まとめ
飲食店における異物混入は、お客様の健康被害と店舗の信用に直結する重要な問題です。近年では、SNSの普及による経営リスクも高まっています。
この問題に対処するためには、予防の徹底から異物混入が発生した際の正確な対応まで、幅広いく備えなければなりません。
そこで、異物混入リスクに関する従業員の危機意識を向上させる「教育」と、「環境整備」の2つが重要になります。。
これらの対策を定期的に改善し、従業員とともに意識を高く持つことで、店舗の信頼を守り、お客様に安全で快適な食事を提供していきましょう。
Q&A
(Q)異物混入とは具体的にどのようなものが含まれますか?
(A)異物混入とは、飲食店や食品製造過程で、料理や製品に意図しない物体が混入することを指します。代表的な異物には、毛髪(体毛)、スタッフのアクセサリー、調理器具の破片、虫などがあります。
(Q)異物混入を防ぐために飲食店がとるべき基本的な対策は何ですか?
(A)基本的な対策としては、従業員の衛生教育の徹底、調理器具や設備の定期的な点検と更新、食材の厳格な検査と管理が必要です。
(Q)異物混入が発生した場合の適切な対応方法とは何ですか?
(A)異物混入が発生した場合、すぐに料理を回収し、事実関係を確認した後、責任者が顧客に対して誠意をもって謝罪し、必要に応じて補償を検討します。
(Q)異物混入を未然に防ぐために外部機関による評価が重要な理由は何ですか?
(A)外部機関による評価を通じて、異物混入のリスクを客観的に把握し、見落としがちな問題点を指摘してもらえるため、より効果的な予防策を講じることができます。
(Q)飲食店で異物混入が発見された際に、顧客とのコミュニケーションで心掛けるべきことは何ですか?
(A)顧客とのコミュニケーションでは、話を遮らずに顧客の意見を最後まで聞き、否定せずに誠実に対応することが重要です。
(Q)異物混入の再発を防止するために店舗が実施すべき継続的な対策は?
(A)異物混入の再発を防止するためには、定期的な従業員の教育、プロセスの見直し、設備のメンテナンスを継続的に実施することが必要です。
(Q)サニクリーンの異物混入無料調査サービスの申し込み方法は?
(A)サニクリーンの公式ウェブサイトから直接異物混入無料調査サービスに申し込むことができます。フォームに必要事項を記入し、送信することで、サービスを利用することができます。
(Q)サニクリーンのサービスを利用することで得られる最大のメリットは何ですか?
(A)サニクリーンのサービスを利用することで得られる最大のメリットは、専門的な知見に基づく具体的な改善提案を受けることで、異物混入のリスクを大幅に低減できる点です。
【監修】
おそうじマイスター(株式会社サニクリーン)
おそうじマイスターとは、株式会社サニクリーンが社内資格として設けている制度で、おそうじに関する正しい知識やノウハウを有した社員を認定するものです。研修や試験に合格した社員が「おそうじマイスター」として認定され、おそうじに関するさまざまな悩みを解決するために、アドバイスや提案、課題解決に向けた取り組みを行います。
<おそうじマイスター紹介ページ>
https://www.sanikleen.co.jp/meister
【参考資料】
厚生労働省「食品等事業者における衛生管理の徹底」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000077216.pdf