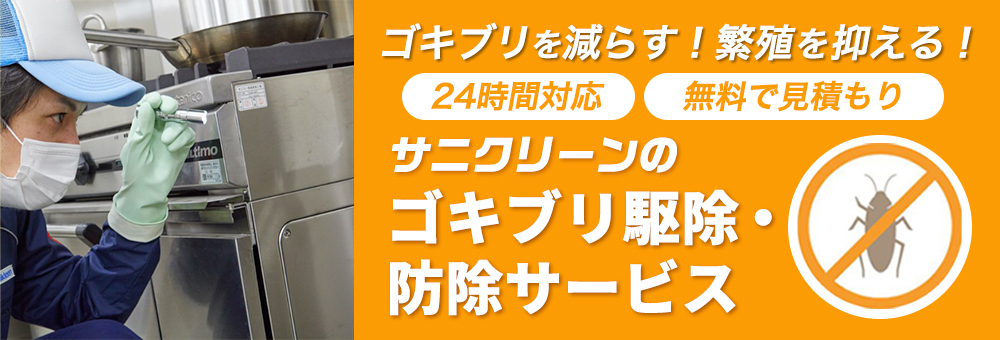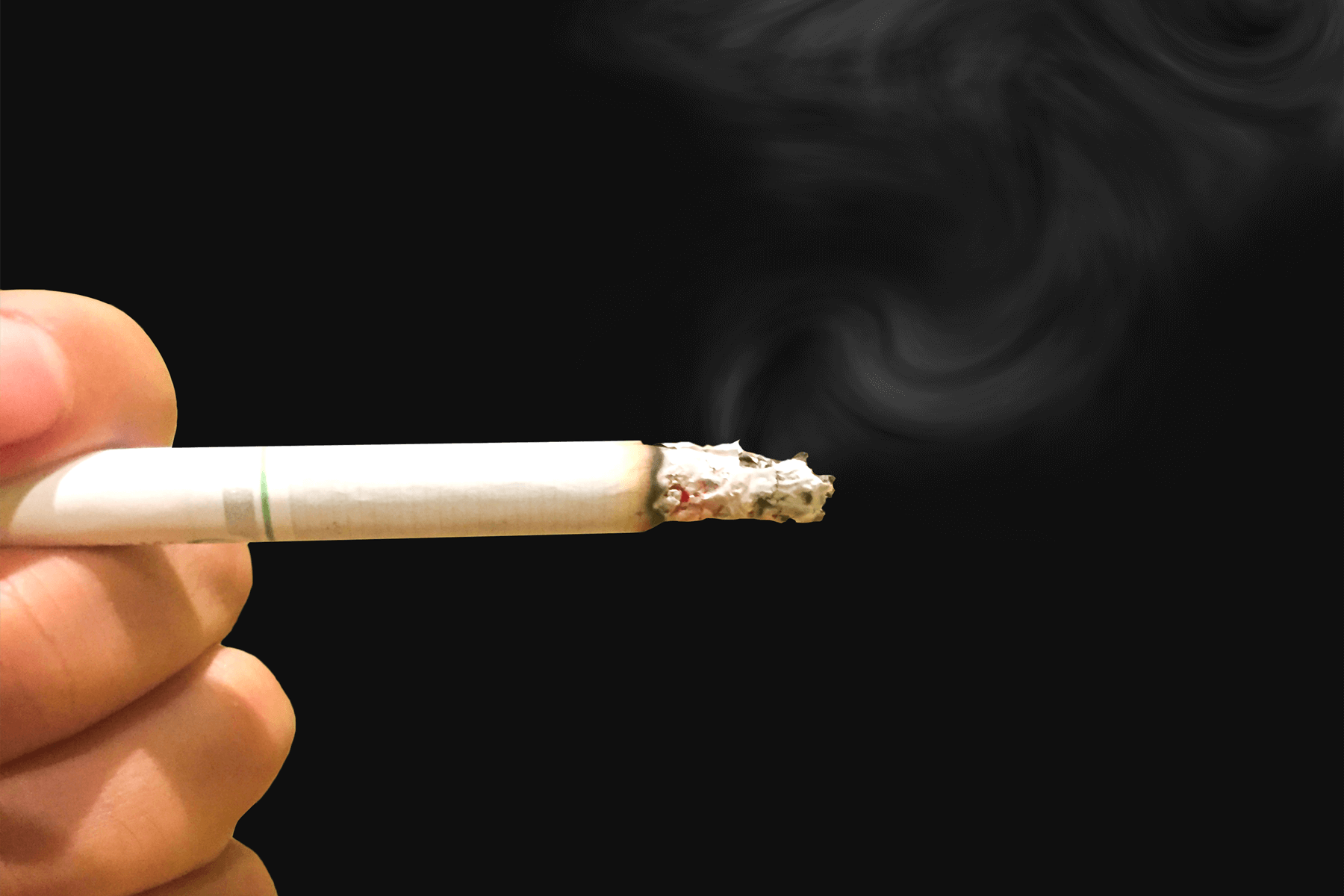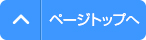建物内部をキレイに保つ「ワック…
飲食店のゴキブリリスク徹底解説~発生原因・被害・対策のすべて
2025.10.01

飲食店におけるゴキブリの発生は、異物混入やSNSでの悪評拡散、保健所からの行政指導につながるなど、経営に甚大なダメージを及ぼす可能性のあるリスクです。たった1匹の目撃が、店舗の信用失墜に直結する例も少なくありません。飲食店は、日々の清掃・衛生管理はもちろんのこと、侵入経路の遮断や専門業者による定期的な点検・防除など、多角的なゴキブリ対策が求められます。
本コラムでは、飲食店のオーナーや店舗責任者に向けて、ゴキブリの発生原因や被害リスク、具体的な予防策、緊急時の対応などについて詳しく解説します。
目次
- 飲食店でゴキブリの発生リスクが高い理由と背景
- 飲食店が被るゴキブリによる主なリスク・被害
- 飲食店でのゴキブリ被害を防ぐ衛生管理と予防策
- 飲食店でゴキブリが発生した際の緊急対応と適切な対処法
- 飲食店がプロのゴキブリ駆除サービスを活用するメリット
- 食品衛生法における飲食店のゴキブリ対策義務
- サニクリーンのゴキブリ駆除・防除サービス
- クレームが発生する前にいかに備えられるかがゴキブリ対策の根幹
- まとめ
- Q&A|飲食店のゴキブリ対策に関するよくある質問
飲食店でゴキブリの発生リスクが高い理由と背景

飲食店は、高温多湿の厨房環境、豊富な食材や残飯、隙間の多い設備構造など、ゴキブリが繁殖しやすいリスク要因がそろっています。さらに、排水口や搬入物からの侵入など、ゴキブリの侵入経路も少なくありません。これらのリスク要因を認識することは、ゴキブリ対策の第一歩となります。ゴキブリの発生・繁殖を招くリスク要因を詳しく見ていきましょう。
高温多湿な厨房環境がゴキブリを呼び寄せる
ゴキブリは温度25~30℃、湿度60%以上の環境を好みます。飲食店の厨房は、調理機器や食洗機による熱、排気による湿度などが合わさることで、ゴキブリにとって理想的な環境になっています。特に、閉店後は換気が止まり、湿気がこもることでゴキブリの活動が活発になります。ゴキブリの発生リスクを低減するためには、厨房をはじめとする店舗全体の温度管理・湿度管理が不可欠です。
豊富な食材・残飯がゴキブリの餌になる
ゴキブリは雑食性で、わずかな食べかすや油汚れがあるだけで生存できます。飲食店では、食材の切れ端や調理中の飛散物、テーブル下のパン屑など、ゴキブリにとっての餌が豊富にあります。さらに、ゴミの放置や分別不備もゴキブリの繁殖を助長する要因です。日々の清掃や食材管理、ゴミの管理が不十分な飲食店ほど、ゴキブリの発生リスクは高くなります。
厨房設備の隙間など、隠れ場所が多い店内構造
ゴキブリは、暗く狭い隙間を好みます。冷蔵庫やオーブンの裏、調理台の下、床下の配管周辺などは清掃が行き届きにくいこともあり、格好の潜伏場所になります。実際に、厨房設備のわずか数ミリの隙間に、100匹を超えるゴキブリが潜んでいる事例もあります。
排水口や搬入物を通じたゴキブリ侵入のリスク
ゴキブリは、屋外からの侵入リスクもあります。排水口や配管の隙間、店舗裏の搬入口、段ボールに付着した卵などは、ゴキブリの代表的な侵入経路です。特に、下水から侵入したゴキブリは衛生リスクが高く、赤痢菌やサルモネラ菌などを媒介する危険性も指摘されています。
飲食店が被るゴキブリによる主なリスク・被害

ゴキブリの発生は、飲食店の経営に甚大な影響を及ぼす可能性があります。飲食店にゴキブリが発生することによる主なリスクを見ていきましょう。
ゴキブリ目撃による顧客の不快感と風評被害
飲食店でゴキブリを目撃した顧客の多くは、強い嫌悪感を抱き、再訪を避ける傾向があります。 さらに、SNSでの拡散によって「不衛生な飲食店」という印象が広がると、直接的な売上減少だけでなく、ブランドイメージの低下につながるリスクもあります。
異物混入による食中毒発生のリスク
ゴキブリは体表やフンに多くの病原菌を保有しており、調理場での接触によって食材や調理器具を汚染します。サルモネラ菌や赤痢菌などによる食中毒が発生した場合、保健所の調査対象となり、営業停止や改善命令が下されるリスクもあります。
なお、令和4年度、保健所等に寄せられた食品に関する苦情件数は東京都全体で4,071件でした。内訳は「有症(腹痛や嘔吐、発熱など症状や病気が現れている状態)」が最多で1,337件(32.8%)、次いで「異物混入」が565件(13.9%)となっています。異物混入の苦情要因を見ると、ゴキブリ等の「虫」が最も多く、185件(32.7%)、次いで人毛等の「動物性異物」が92件(16.3%)となっています。
※参考:食品衛生責任者・お知らせ版|令和6年6月1日|東京都
https://www.toshoku.or.jp/eiseijigyo/backnumpdf/20240603-200.pdf
衛生不備が招く行政指導・営業停止のリスク
HACCP(ハサップ)の制度化以降、飲食店には衛生管理の実施・記録が義務付けられています。ゴキブリの発生は、衛生管理の不備として保健所の立ち入り検査や指導対象となることがあり、重大な場合は営業停止命令が下るリスクもあります。
飲食店でのゴキブリ被害を防ぐ衛生管理と予防策
ゴキブリ対策の基本は、リスク要因を取り除く「予防管理」です。日常の清掃、食材やゴミの管理、侵入経路の封鎖、従業員の教育、モニタリングなどの取り組みが重要です。
厨房・店内の清掃徹底と衛生管理のポイント
ゴキブリは、食べかすや油汚れが残る場所に集まります。特に調理機器の下、排水口周辺、棚の隙間は清掃が不十分になりやすいため、定期的な清掃が不可欠です。清掃の際は、目に見える汚れを取り除くだけでなく、機器の分解清掃や専用洗剤を使った油汚れの除去なども重要です。
▼関連記事
飲食店清掃の要!厨房をキレイにせよ!
https://www.sanikleen.co.jp/biz/seisou/detail/696.html
食材の適切な保管と在庫管理の徹底
食材は密閉容器で保管し、棚から10cm以上離して置くことで、ゴキブリが侵入しにくい環境をつくることができます。また、在庫管理を徹底することで、賞味期限切れや長期放置された食材が発生しにくくなり、ゴキブリの餌を減らせます。特に、乾物類や調味料はゴキブリの好物なので、保管場所の衛生管理と整理整頓が不可欠です。
残飯・ゴミの適切な処理と毎日の廃棄徹底
ゴミの管理が徹底されていないことは、ゴキブリが繁殖する大きな要因の一つです。蓋付きのゴミ箱を使用することや、営業終了ごとにゴミを廃棄することは基本です。加えて、ゴミ置き場は毎日洗浄・消毒を行い、発生源を根本から断つことが大切です。
建物内外の点検とゴキブリ侵入経路の封鎖
ゴキブリの主な侵入経路は、排水口や配管の隙間、搬入口です。また、段ボールに付着した卵から侵入することもあります。ゴキブリの侵入リスクを低減するためには、排水トラップの設置、隙間のコーキング、ドア下部の封鎖など、建物全体をチェックして侵入経路を封鎖する必要があります。段ボールの保管・廃棄ルールの見直しも重要です。
従業員への衛生教育とマニュアル整備
ゴキブリのリスクを低減するためには、管理者だけでなく、全従業員の意識改革が欠かせません。HACCPの考え方でも、現場の従業員が日常的に衛生行動を実践することが前提とされています。清掃チェックリストを活用することや、ゴキブリ発見時の対応手順をマニュアル化することで、従業員の衛生意識を高めることが重要です。
捕獲トラップ設置などによる定期モニタリング
ゴキブリは夜行性なので、目視の確認だけで発生状況を把握するのは困難です。たとえば、定期的に粘着トラップを設置することで、発生の有無や侵入経路を可視化するのは効果的です。また、専門業者にモニタリングを依頼すれば、データとしてゴキブリの発生状況を把握できます。侵入経路や発生状況を正確に把握したうえで、ゴキブリを寄せ付けない環境づくりを進めることが重要です。
▼関連記事
飲食店の「異物混入」対策|虫や毛髪など発生原因も紹介
https://www.sanikleen.co.jp/biz/seisou/detail/3318.html
飲食店でゴキブリが発生した際の緊急対応と適切な対処法

店内でゴキブリを発見した場合は、迅速かつ適切な初動対応が求められます。一連の対処法を詳しく見ていきましょう。
店内でゴキブリを発見したときに取るべき行動
店内で生きたゴキブリを発見したら、すみやかに駆除します。特に、営業中は顧客の目に触れないよう、迅速な対応が求められます。従業員の迅速な対応を促すためには、事前にゴキブリ発見時の対応手順を共有しておくことが大切です。また、後の発生源特定に活かすため、発見場所や発見時間を記録しておきましょう。
応急的な駆除方法
即時対応としては、スプレータイプの殺虫剤や捕獲器の使用が効果的です。ただし、厨房や客席で、エアロゾル型殺虫剤を使用するのは避けなければいけません。食品衛生管理上は、毒餌型ベイト剤や粘着トラップを併用し、衛生と顧客の安全を確保することが推奨されています。
被害状況の確認と発生源の特定
一時的にゴキブリを駆除しても、発生源を突き止めない限り再発のリスクは避けられません。厨房機器の裏、排水口、壁の隙間、搬入経路などを徹底的に調査し、ゴキブリの「ローチサイン」がないか確認しましょう。ローチサインとは、ゴキブリが活動・繁殖している可能性を示す「痕跡」のことであり、代表的なものに、フン、卵鞘(らんしょう)、脱皮殻、死骸、特有の臭気などがあります。
▼関連記事
ローチサインとは?飲食店が知っておくべきゴキブリ発生の見分け方と対策
https://www.sanikleen.co.jp/biz/seisou/detail/3371.html
顧客からクレームを受けた場合の適切な対応
ゴキブリ目撃に関するクレームがSNSなどで拡散されると、風評被害に発展するリスクがあります。顧客からゴキブリに関するクレームを受けた場合は、第一に誠意をもって謝罪し、対応状況を説明することが重要です。加えて、今後の再発防止策(定期駆除の実施や清掃体制の強化)を具体的に伝えることで、信頼回復に努めましょう。
▼関連記事
飲食店のゴキブリクレーム徹底対策ガイド – 発生原因から予防策・クレーム対応まで
https://www.sanikleen.co.jp/biz/seisou/detail/3373.html
専門業者への相談と再発防止策の実行
飲食店は、チャバネゴキブリのように繁殖力が強いゴキブリが多いため、自力で対策をするには限界があります。そのため、専門業者の力を借りることをおすすめします。ゴキブリ駆除の専門業者は、適切な薬剤を使ってゴキブリを駆除するだけでなく、発生源の調査や再発防止策の立案まで行います。専門業者と定期契約をすることで、ゴキブリ発生のリスクが低い環境を長期的にわたって維持することができます。
飲食店がプロのゴキブリ駆除サービスを活用するメリット
飲食店におけるゴキブリ発生は、店舗の売上やブランド価値を損なう重大なリスクになります。徹底したリスク対策が求められますが、自力での対策には限界があるのも事実です。そこでおすすめしたいのが、専門業者によるゴキブリ駆除サービスを導入することです。こちらでは、自力でゴキブリ対策をする場合の懸念点のほか、専門業者を活用するメリットや業者選びのポイントなどについて解説します。
自分で行うゴキブリ駆除の限界と隠れたリスク
市販の殺虫剤やトラップを使えば、目に見えるゴキブリを一時的に減らすことはできますが、巣ごと駆除するのは困難です。チャバネゴキブリのように小型で隠れやすい種は、厨房機器の裏や配管周りに潜伏しており、表面的な対策だけで再発を防ぐのは困難です。また、不適切な薬剤使用が、食材や調理器具への二次汚染につながるリスクもあります。
プロの駆除業者に任せることで得られる効果
専門業者は、ゴキブリの発生源を徹底調査したうえで、発生状況や店舗の構造を踏まえて最適な薬剤を選定し、効果的な施工を行います。これにより、ゴキブリを根本から駆除することができます。加えて、再発防止対策や衛生指導も行うため、長期的に衛生レベルの維持・向上を図ることができます。
ゴキブリ駆除業者を選ぶ際のチェックポイント
ゴキブリ駆除の専門業者を選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。
・実績:飲食店向けの駆除事例が豊富か?
・施工保証:駆除後に再発した場合の無料対応や保証期間の有無は?
・費用の透明性:見積もり段階で作業範囲や追加費用が明確になっているか?
・使用薬剤の安全性:食品を扱う環境に安全な薬剤を使用しているか?
・定期契約:定期的なゴキブリ防除やモニタリング、衛生指導に対応しているか?
なかでも重視したいのが定期契約です。単発でゴキブリを駆除してもらっても、時間とともに再発のリスクは高くなっていきます。定期契約であれば、1~3ヶ月に1回程度のペースで防除やモニタリングをしてもらえるため、ゴキブリの発生リスクが低い環境を維持できます。特に、HACCP対応が求められる飲食店の場合は、保健所対策という意味でも専門業者と定期契約をしておいたほうが安心です。
なお、飲食店におけるゴキブリ駆除の費用相場は、単発の施工で3~7万円程度、定期契約で月1~3万円程度です。
▼関連記事
飲食店のゴキブリ対策の正解|効果的なサービスも紹介
https://www.sanikleen.co.jp/biz/seisou/detail/3320.html
食品衛生法における飲食店のゴキブリ対策義務

飲食店におけるゴキブリ対策は、単なる衛生管理ではなく、食品衛生法や各自治体の条例によって求められている義務です。特に、HACCP制度化以降は、計画的・継続的な対策が求められるようになっています。
食品衛生法・条例が定める衛生管理基準と害虫防除
食品衛生法および各自治体の条例では、飲食店に対し、施設内の清掃や害虫・ねずみの防除を行う義務が規定されています。これらの規定に違反した飲食店は改善命令の対象となるリスクがあります。
保健所による抜き打ち検査と違反時の処分
飲食店は、保健所による定期検査や抜き打ち検査を受けることがあります。ゴキブリの発生や衛生不備が確認された場合、指導や改善命令が下されるだけでなく、重大な場合には営業停止の処分を受けるリスクもあります。
HACCPに基づく衛生管理と害虫駆除対策
HACCPの制度化により、すべての飲食店は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施することが義務付けられました。これには、ゴキブリなどの害虫防除も含まれており、発生状況の記録や対策の実施履歴を残すことが求められています。
サニクリーンのゴキブリ駆除・防除サービス
ゴキブリのリスクに備えたい飲食店におすすめしたいのが、サニクリーンの「ゴキブリ駆除・防除サービス」です。
ベイト剤方式を採用し、ゴキブリの習性を利用して巣ごと根絶。再発を防ぐ年間管理プログラムで、良好な衛生環境を持続できます。店舗の営業時間中でも施工でき、準備や片付けも不要。少量のベイト剤で最大限の効果を発揮できるよう施工するので、まわりの環境や人体に影響を及ぼす心配はありません。地下の店舗やテナントが密集したビルなど、換気が万全でないところや締め切った空間でも安心です。
クレームが発生する前にいかに備えられるかがゴキブリ対策の根幹
ゴキブリの発生や異物混入など、衛生管理上の不備に対する消費者の目は、年々厳しさを増しています。その背景には、食の安全に対する社会的関心の高まりがあります。実際に、大手食品メーカーの商品に小動物の一部が混入した事例は全国ニュースとして大きく報じられるなど、衛生トラブルは深刻な社会的問題として扱われるようになっています。
さらに昨今は、SNSや口コミサイトといった拡散力の高い情報媒体が一般化しており、衛生トラブルが発生した事実は瞬く間に社会全体へ広がります。ゴキブリの目撃情報や異物混入に関する投稿がひとたび拡散されれば、一夜にして飲食店の信頼は地に堕ちてしまうでしょう。
このような状況を踏まえると、ゴキブリ対策は「未然防止」が極めて重要であることが分かります。衛生トラブルを経験した飲食店からは、「もっと早い段階で手を打っていれば、こんなことにはならなかった」といった声も聞かれます。これは、定期的な点検やモニタリングを通した「トラブルの芽の早期発見」こそが、飲食店の信頼を守るうえで最も効果的な手段であることを示しています。
とはいえ、どれだけ対策を講じても、衛生リスクをゼロにすることは困難であり、厳格な管理を行っている大手企業でさえ衛生トラブルを起こしているのが現状です。だからこそ今後は、未然防止に加えて、万が一の事態が発生した際に迅速かつ適切な対応をするための「総合的なリスクマネジメント体制」の構築が重要になってきます。
そのためには、従業員の衛生意識を高める教育はもちろん、ゴキブリの発生、異物混入、SNSの炎上などトラブル別の対応マニュアルの整備や、定期的な訓練が不可欠です。リスクを可視化・予測・管理する一連の体制づくりこそが、飲食店における持続的な信頼構築の鍵となるのです。
まとめ
飲食店にとって、ゴキブリの発生は避けて通れない経営リスクですが、正しい知識と的確な対策によってリスクの低減を図ることは可能です。
本コラムで解説したように、ゴキブリは、温度、湿度、餌、隠れ場所、侵入経路といった条件がそろうことで繁殖します。これらを意識して、厨房の清掃やゴミの処理、侵入防止対策を徹底するとともに、専門業者によるゴキブリ駆除・防除・モニタリングサービスを組み合わせることで、ゴキブリが発生しにくい衛生的な環境を維持することができます。
「1匹でも見つけたら100匹いると思え」と言われるゴキブリ対策ですが、裏を返せば「地道な対策が100の被害を防ぐ」ことにつながるということです。平時から備えを固めておくことが、ゴキブリの発生・被害拡大を防止し、消費者の信頼を支える土台となるはずです。
Q&A|飲食店のゴキブリ対策に関するよくある質問
Q.1 ゴキブリが1匹でも出たら駆除業者を呼ぶべき?
A. 1匹でも見つけた場合は、専門業者への相談を検討すべきです。
飲食店でゴキブリを1匹見かけた場合、その背後には数十~数百匹の巣が潜んでいる可能性があります。特に、チャバネゴキブリは繁殖力が高く、短期間で爆発的に数を増やします。早期に専門業者に相談することで、被害を最小限に抑えられます。
Q.2 ゴキブリはどの時期に発生しやすいですか?
A. ゴキブリは春から夏にかけて最も活発になります。
特に、5月〜9月の高温多湿な時期に活発化し、繁殖が進みます。ただし、飲食店の厨房は暖房や熱気の影響で年中暖かく、湿気も多いため、冬でも発生リスクはあります。季節を問わず、通年で対策をすることが重要です。
Q.3 店舗でのゴキブリ発見時、顧客対応はどうすればよい?
A. 顧客の感情に配慮し、真摯に謝罪をすることが最優先です。
否定や言い訳をせず、「ご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪しましょう。そのうえで、適切な補償(返金、代替品、クーポン等)を提案します。加えて、ゴキブリを除去した旨や清掃をした旨、再発防止のための対策について説明します。重要なのは、顧客に「店が真剣に受け止め、すぐに対処しようとしている」と感じてもらうことです。
Q.4 飲食店での異物混入による行政処分はありますか?
A. 状況次第では、指導や営業停止処分の可能性もあります。
食品衛生法では、飲食店に対して衛生管理と異物混入防止が義務付けられており、重大なケースでは営業停止や営業許可の取消しが行われることもあります。発生時の初動対応と、日常のHACCP対応・記録管理が重要です。
Q.5 ゴキブリ対策にHACCPはどのように関係しますか?
A. HACCPでは、衛生管理の一環として害虫防除も求められています。
HACCPに基づく衛生管理では、ゴキブリを含む害虫の侵入・繁殖・混入を防ぐ措置と記録が必要です。定期的なチェックと異常時の対応ルール整備、業者との連携など、総合的なリスク管理体制の構築が求められます。
Q.6 ゴキブリ駆除の費用はどのくらいかかりますか?
A. 単発施工で3〜7万円、定期契約で月1〜3万円が相場です。
具体的な金額は、店舗の広さやゴキブリの発生状況によって変わってきます。数社に問い合わせをして、相見積もりを取ることをおすすめします。
Q.7 店内のどこにゴキブリが潜みやすいですか?
A. 調理機器の裏・排水口・配管周辺・壁の隙間などは、潜伏リスクが高い場所です。
ゴキブリは狭く暗く湿った場所を好むため、厨房機器の裏や床下、調味料置き場、ゴミ箱周辺などは要注意です。これらの場所は日常清掃が届きにくく、発見も遅れやすいため、定期的な点検と清掃が欠かせません。
Q.8 ゴキブリの餌になりやすいものには何がありますか?
A. 食材くず、油汚れ、調味料、段ボールなどが該当します。
ゴキブリは雑食で、食品だけでなく段ボールや髪の毛なども餌にします。調理中の飛び散りや床の汚れ、ゴミの放置が餌場を作る原因となるため、こまめな清掃とゴミの即日処理が重要です。
Q.9 駆除業者を選ぶ際のポイントは?
A. 実績や保証制度、費用の明確さや薬剤の安全性などがポイントです。
飲食店におけるゴキブリ駆除の実績、施工後の保証対応、見積もりの内訳の明確さなどを確認しましょう。また、厨房に薬剤を使う場合は、食品への安全性を確認することも重要です。
Q.10 ゴキブリ発生を防ぐ日常習慣には何がありますか?
A. 清掃やゴミ処理、食材の密閉保管、点検などが挙げられます。
基本的な対策として、調理後の即時清掃、ゴミの即日廃棄、食材の密閉保管、厨房の定期点検を習慣にすることが重要です。また、従業員に衛生教育を行い、衛生意識を高めることも大切です。
<参考文献>
HACCP(ハサップ)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
HACCP ハサップ・危害要因分析重要管理点)とは – 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000896866.pdf
衛生管理基準の解説|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000706449.pdf
ゴキブリが媒介する感染症|殺虫剤|フマキラー製品情報サイト
https://fumakilla.jp/column/gokiburi/1/