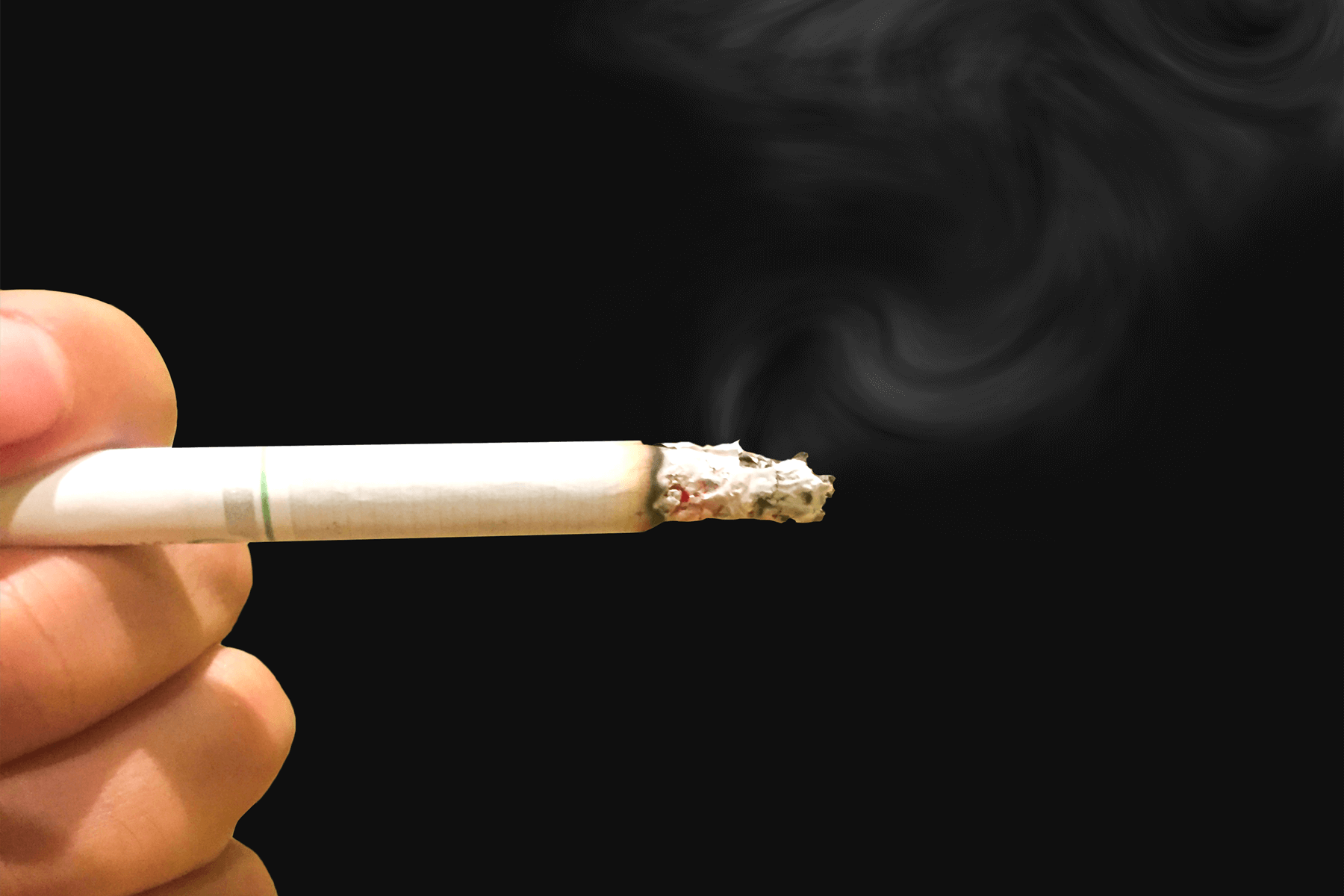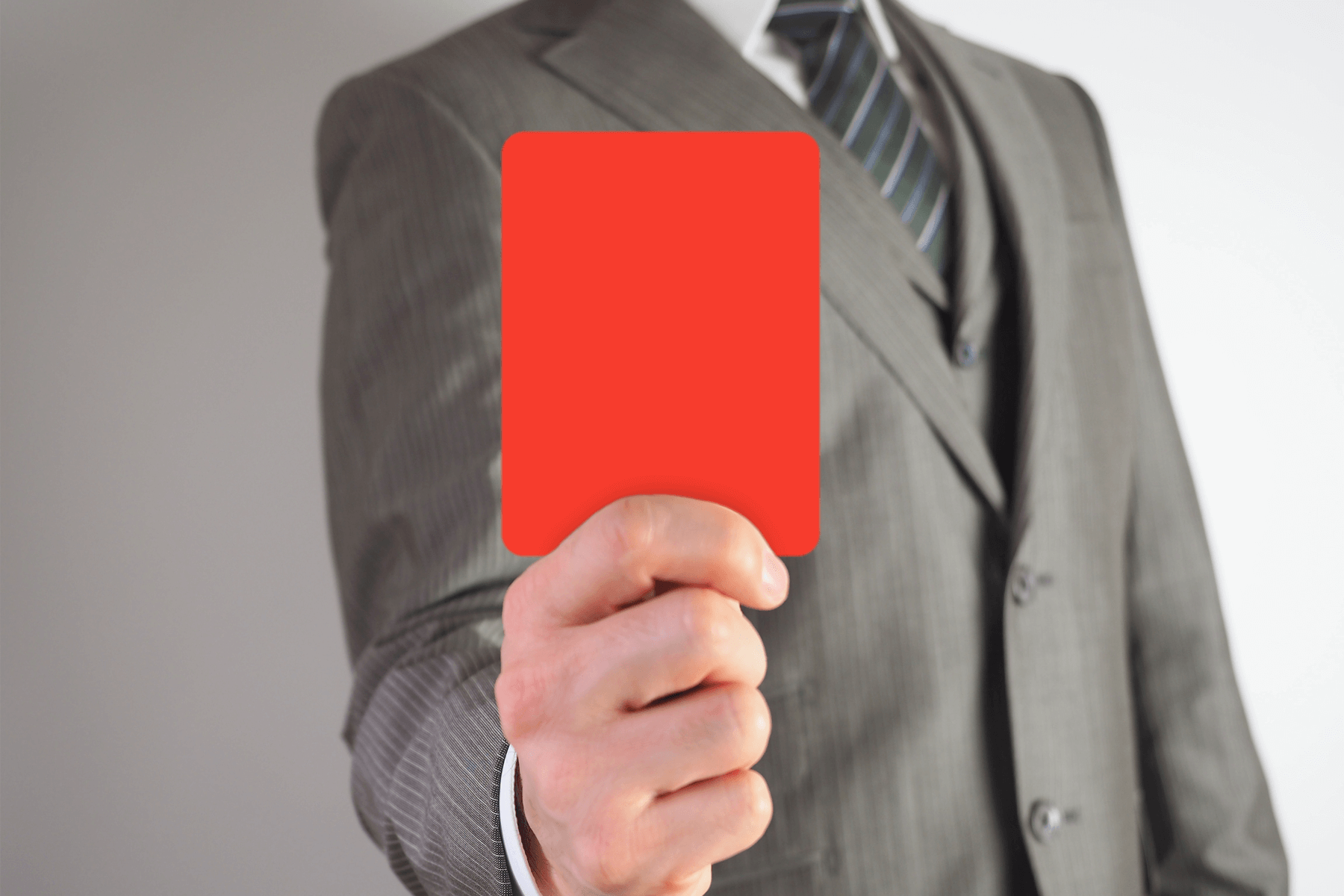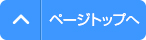梅雨に多発する食中毒を防止せよ…
飲食店の害虫駆除ガイド:日々の対策と業者選びのポイント
2025.11.10

飲食店にとって、ゴキブリやネズミ、ハエなどの害虫は「一匹でも見つかれば致命的」といわれるほど大きなリスクを伴います。飲食店で害虫を目にした顧客にSNSで拡散されてしまうと、店舗のイメージダウンは避けられません。万が一、害虫が原因で異物混入や食中毒の被害が出てしまったら、顧客離れによる売上低下だけでなく、営業停止を余儀なくされる可能性もあります。そこで本記事では、飲食店で発生しやすい害虫の特徴や発生原因のほか、予防・駆除の方法、専門業者の選び方などについて解説していきます。
目次
飲食店に多い害虫〜ゴキブリ・ネズミ・ハエの特徴や発生原因

飲食店にとって、害虫の発生は衛生面・経営面の双方に大きなリスクをもたらす深刻な問題です。特に、ゴキブリ、ネズミ、ハエは、飲食店で発生しやすい代表的な害虫(害獣)です。的確な対策・駆除をおこなうため、これらの害虫の特徴や発生原因・侵入経路を押さえておきましょう。
ゴキブリ:繁殖力が強く食中毒の原因にもなる害虫
飲食店で特に警戒すべき害虫の一つがゴキブリです。日本の飲食店でよく発生するのはチャバネゴキブリとクロゴキブリで、いずれも繁殖力が強いのが特徴です。チャバネゴキブリは1つの卵鞘(らんしょう:メスのゴキブリが産み落とすカプセル状の卵の集合体)に30個前後の卵を持ち、20日ほどで孵化するため短期間で急激に増える可能性があります。
●主な特徴
・繁殖力が非常に強く、短期間で大量発生する。
・暗く湿った場所を好み、夜間に活発に活動する。
・雑食性で強い生命力を持ち、わずかな水分でも生き延びる。
・狭い場所に潜む習性があり、厨房設備の裏や排水溝、什器の隙間などにいることが多い。
●主な発生原因
・厨房の食べかすや油汚れ
・排水溝やグリストラップの清掃不足
●主な侵入経路
・卵が付着したダンボールが搬入されることで侵入する。
・排水管や通気口、壁の隙間など建物の構造的な穴から侵入する。
・店舗外のゴミ置き場から侵入する。
▼関連記事
ローチサインとは?飲食店が知っておくべきゴキブリ発生の見分け方と対策
ネズミ:感染症や設備被害を招く厄介な害虫(害獣)
飲食店でしばしば問題となるのがネズミ類です。都市部の飲食店ではドブネズミやクマネズミが、郊外の飲食店ではハツカネズミが多く発生します。
●主な特徴
・優れた嗅覚と聴覚を持ち、わずかな食材のニオイでも引き寄せられる。
・繁殖力が強く、一度侵入すると短期間で個体数が急増する。
・狭い隙間を通り抜け、壁内や天井裏を移動する。
・夜行性であり、昼間は姿を見せなくても夜間に活発に活動する。
●主な発生原因
・厨房や客席の食べ残しや食材かす
・排水溝やグリストラップの清掃不足
・食材の保管不備(密閉容器を使わない、棚に隙間があるなど)
●主な侵入経路
・店舗外のゴミ置き場から侵入する。
・店舗の出入口や食材の搬入ルートから侵入する。
・配管や通気口の隙間、壁の穴から侵入する。
ハエ:食品を汚染し不快感を与える害虫
飲食店で発生しやすい害虫のなかでも、ハエは厨房や客席の衛生環境に直接的な影響を与えます。繁殖サイクルが早く、条件が揃えば短期間で大量発生するため、早期の対策が不可欠です。
●主な特徴
・繁殖サイクルが早く、数日で卵から成虫になる。
・イエバエは食品に直接とまり、唾液や排泄物で病原菌を媒介する。
・ショウジョウバエはアルコールや甘いものに誘引され、酒類や果物の周囲に群がる。
・チョウバエは排水溝やグリストラップに発生し、湿気の多い環境を好む。
●主な発生原因
・生ゴミの放置
・グリストラップや排水溝の清掃不足
・食材の保管不備(果物・酒類・調味料の出しっぱなしなど)
・高温多湿の厨房環境
●主な侵入経路
・店舗の出入口や食材の搬入ルート、窓の隙間から侵入する。
・外部から持ち込まれる食材や容器に付着している。
飲食店でできる害虫予防・害虫駆除の方法

飲食店で害虫を完全にゼロにするのは容易ではありませんが、日々の取り組み次第で発生リスクを下げることは可能です。ゴキブリやネズミ、ハエなどの害虫(害獣)は、食材や残飯、排水溝の汚れなどを好みます。そのため、日常の清掃や衛生管理を徹底することが第一歩となります。飲食店における害虫予防・害虫駆除の方法について解説します。
日常清掃と衛生管理で害虫の発生を防ぐ
飲食店における害虫対策の基本は、日常清掃と衛生管理の徹底です。ゴキブリやネズミ、ハエなどの害虫は、食べかすや油汚れ、水分や生ゴミなどの「餌」と「住みか」を求めて店内に侵入し、繁殖します。そのため、こうした要因を日々の清掃で取り除くことが重要です。主なポイントは以下のとおりです。
●厨房・ホールの清掃
・営業終了後には床のモップがけ、テーブル・調理台の拭き上げをおこなう。
・調理機器の下や冷蔵庫の裏など、ゴミや油が溜まりやすい「死角」を重点的に掃除する。
●排水溝・グリストラップの清掃
・コバエやチョウバエは、排水溝やグリストラップに溜まった有機物を餌に繁殖する。
・毎日の簡易清掃に加え、週1回程度は徹底的な洗浄をするのが望ましい。
●ゴミ管理の徹底
・生ゴミは必ずフタ付き容器に入れ、閉店後は店外のゴミ置き場へすみやかに搬出する。
・ゴミ置き場も定期的に清掃・消毒し、害虫の発生源にならないように管理する。
●食材・備品の適切な保管
・食材は必ず密閉容器に入れて保管し、開封後の原材料は冷蔵・冷凍庫で管理する。
・ダンボールは害虫の隠れ場所になりやすいため、搬入後はすみやかに廃棄する。
▼関連記事
建物環境を見直して害虫の侵入経路を遮断する
飲食店で害虫の発生を防ぐためには、建物環境の見直しが欠かせません。ゴキブリやネズミ、ハエなどの害虫は、わずかな隙間や構造的な弱点を利用して侵入します。そのため、侵入経路そのものを遮断することが長期的な予防につながります。主なポイントは以下のとおりです。
●出入口・窓
・自動ドアや出入口の隙間からゴキブリやハエが侵入するケースが多い。
・防虫カーテンやエアカーテンを設置し、窓には網戸を取り付ける。
●排水溝・グリストラップ
・コバエやチョウバエの主要な発生源になる。
・定期清掃に加え、防虫トラップや専用フタの設置で物理的に侵入を防ぐ。
●配管・ダクト・電気配線
・ネズミやゴキブリは配管や壁の隙間から侵入する。
・コーキング材や防鼠パテで隙間を埋め、金網や防鼠カバーを取り付ける。
●ゴミ置き場・搬入口
・食材の搬入時やゴミの搬出時に害虫が侵入しやすい。
・ゴミ置き場は密閉性を確保し、食材の搬入口は清掃と点検を徹底する。
●厨房機器の周囲
・冷蔵庫や製氷機の裏側、什器の下などは死角になりやすく、害虫が潜む温床となる。
・機器を設置する際に壁との間隔を空け、定期的に点検・清掃できる環境を整える。
市販の害虫駆除グッズを活用する
日常清掃や侵入経路の遮断に加えて、市販の害虫駆除グッズを活用することで、害虫対策を強化することができます。特に、初期段階で繁殖を抑えるのに効果的であり、被害拡大を防げます。代表的な害虫駆除グッズと活用方法は以下のとおりです。
●殺虫剤
・ベイト剤(毒餌タイプ):ゴキブリ対策に有効。巣に持ち帰らせて連鎖的に駆除する仕組み。冷蔵庫裏や流し台下、什器の隙間などに設置する。
・スプレータイプ:目視できる害虫の即効駆除に有効。ただし、食品や食器にかからないよう注意が必要。
●捕獲器(トラップ)
・粘着トラップ:ゴキブリやネズミの通り道に設置して捕獲する。生息状況の調査にも役立つ。
・電撃殺虫器(ライトトラップ):紫外線でハエ・コバエを誘引し、電撃または粘着シートで捕獲。厨房やホールに設置可能。
●忌避剤・防虫グッズ
・ハーブ由来の忌避剤(ラベンダー、ミントなど)を出入口や窓際に設置すると、ハエやゴキブリを寄せ付けにくくなる。
・防鼠スプレーや超音波装置はネズミ対策に有効。ただし、効果に個体差がある。
●その他
・ドレンキャップ:エアコンの排水ホースから侵入するゴキブリ防止に効果的。
・防虫ネット:換気扇や通気口に取り付けることで、小型害虫の侵入を防止できる。
飲食店が害虫駆除業者に依頼すべきケースとメリット

飲食店における害虫(害獣)対策は、日常清掃や害虫駆除グッズの活用によってある程度の効果は見込めますが、自力での対応には限界があるのも事実です。短期間で急激に数が増えてしまった場合などは、専門の害虫駆除業者に依頼するのが賢明です。
大量発生した場合は害虫駆除業者に依頼する
飲食店でゴキブリやネズミ、ハエなどの害虫が大量に発生してしまった場合、自力で駆除するのは困難です。これらの害虫は繁殖力が強く、少しでも残存個体がいれば再び増えてしまいます。「害虫を毎日目撃している」「多数の害虫を複数箇所で目撃している」「自力で駆除したが再び発生した」といった場合は、専門の害虫駆除業者に依頼するのが最善策です。
害虫駆除業者に依頼するメリット
専門の害虫駆除業者に依頼するメリットとしては、次の5点が挙げられます。
①徹底的な駆除
害虫駆除業者は、害虫の種類や生息環境を調査(モニタリング)し、その結果に基づいて最適な駆除方法を選定します。業務用のベイト剤や残留噴霧、空間処理を組み合わせ、隠れた巣や卵まで徹底的に駆除します。一時的に減るだけでなく、長期的な効果が期待できるのが大きなメリットです。
②再発防止と環境改善
害虫駆除業者は、単に害虫を駆除するだけでなく、建物の隙間塞ぎや排水溝の改善、防虫ネットの設置など、再発を防ぐための環境改善策を提案・施工してくれます。害虫駆除業者の力を借りることで、害虫を「寄せ付けない店舗環境」を構築できます。
③法令遵守と記録管理
食品衛生法およびHACCP制度では、ネズミ・害虫対策の実施と記録が義務付けられています。多くの害虫駆除業者は、施工内容や点検結果を報告書として提供してくれるため、監査や保健所の立ち入り検査にも対応できます。
④緊急対応と定期契約
多くの害虫駆除業者は、24時間対応や定期契約を提供しています。突発的な害虫トラブルに迅速に対応できるほか、定期契約を選択することで害虫発生リスクの低い衛生的な店舗環境を維持できます。
▼関連記事
飲食店のゴキブリ対策の正解|効果的なサービスも紹介
飲食店の害虫駆除業者の選び方と費用相場

飲食店にとって害虫(害獣)駆除業者の選定は、店舗の衛生と経営を守る重要な判断になります。信頼できる業者を見極めるためのチェックポイントや費用相場について解説します。
害虫駆除業者を選ぶ際のチェックポイント5つ
①資格・許認可の有無
・「防除作業監督者」「ペストコントロール技術者」などの国家資格・認定資格を持つスタッフが在籍しているか
・建築物衛生法や食品衛生法に基づく業務を適切に実行できる体制が整っているか
②実績・専門性
・同業種の飲食店での害虫駆除実績が豊富か
・ゴキブリ・ネズミ・ハエなど、それぞれの害虫駆除に関する専門的な知見・ノウハウを持っているか
③調査・見積もりの透明性
・事前に現地調査をおこない、状況に応じた具体的なプランを提示してくれるか
・見積書の記載が「〇〇一式」などの曖昧なものではなく、「作業内容」「使用薬剤」「回数」「保証範囲」などが明記されているか
④使用薬剤と安全性
・厨房や客席に使用する薬剤は食品衛生上、安全なものか
・低毒性の薬剤や環境に配慮した薬剤を使用しているか
⑤契約後のサポート体制
・害虫駆除後のアフターフォロー体制は整っているか
・緊急時に迅速に対応できる体制(24時間対応など)があるか
害虫駆除業者の費用相場
害虫駆除業者の費用は、契約内容によって変わってきます。害虫駆除業者の契約は、大きく「スポット契約」と「定期契約(年間保守契約)」の2つがあります。スポット契約は文字どおり単発で害虫を駆除する契約で、定期契約(年間保守契約)は月に1回〜数回の点検・駆除をおこなう契約です。それぞれの費用相場は以下のとおりです。
①スポット契約の費用相場
・ゴキブリ駆除:2万〜5万円前後(厨房・ホールなど店舗全体を対象)
・ネズミ駆除:3万〜10万円前後(粘着シート設置、防鼠工事を含む場合はさらに高額)
・ハエ・コバエ駆除:2万〜5万円前後(排水溝・グリストラップの処理を含む)
②定期契約(年間保守契約)の費用相場
・月額:1万〜3万円程度
・年間:12万〜36万円程度
害虫被害が軽度で、一時的な駆除を希望する場合はスポット契約でも問題はありませんが、どうしても再発のリスクが付きまといます。飲食店は、法令遵守の観点からも定期契約が推奨されます。
害虫が飲食店にもたらすリスクと害虫駆除の重要性
決して大げさな話ではなく、わずか1匹の害虫(害獣)によって飲食店の存続が脅かされるケースがあります。飲食店における害虫発生の具体的なリスクと、害虫駆除の重要性について解説します。
食中毒や異物混入のリスク
ゴキブリやネズミ、ハエなどの害虫が、食中毒や異物混入の原因になることがあります。
①食中毒
・ゴキブリは、サルモネラ菌や大腸菌、赤痢菌など数十種類以上の病原菌を媒介します。
・ネズミは、レプトスピラ症やサルモネラ症などの感染症を拡散させるおそれがあります。
・ハエは、生ゴミや排泄物に触れた後、食品にとまり、細菌やウイルスを運び込みます。
・これらの病原体が食品や食器に付着すると、食中毒が発生する可能性があります。食中毒は、顧客に深刻な健康被害をもたらすおそれがあります。
②異物混入
・ゴキブリの死骸や卵鞘、ネズミの毛や糞尿、ハエの死骸などが食品や料理に混入する可能性があります。
・仮に健康被害が出なくても、「虫が混入していた」というだけで、重大なクレームにつながることがあります。
▼関連記事
梅雨の食中毒を防げ!飲食店が気をつけるべき清掃ポイント
▼関連記事
飲食店の「異物混入」対策|虫や毛髪など発生原因も紹介
イメージダウンや売上低下のリスク
飲食店におけるゴキブリやネズミ、ハエなどの害虫は、目撃した顧客に強烈な不快感を与えます。たとえ健康上の被害がなくても、顧客に「この店は不衛生だ」という印象を植え付けてしまいます。
①クレーム・来店拒否
・飲食店で害虫を目撃した顧客からクレームが入り、保証を求められるケースがあります。
・「不衛生な店」というイメージは簡単には払拭できず、害虫を目撃した顧客は二度と来店しなくなります。
②悪評の拡散・イメージダウン
・「料理に虫が入っていた」「床にゴキブリがいた」といった口コミがSNSなどで拡散されると、店舗の悪評は一気に広まります。
・店舗のイメージダウンは避けられず、消費者の信用は大きく低下します。
③顧客離れ・売上低下
・害虫発生による悪評は、新規顧客の来店を妨げるだけでなく、既存顧客の信頼も損ないます。
・一度失墜した信頼を回復するのは難しく、長期的な売上低下から閉店に追い込まれる可能性もあります。
▼関連記事
飲食店のゴキブリクレーム徹底対策ガイド – 発生原因から予防策・クレーム対応まで
行政指導や営業停止などの法的リスク
日本では、食品衛生法や自治体の条例に基づき、飲食店に衛生管理が義務付けられています。飲食店における害虫発生は、法的リスクに直結する課題でもあります。
①食品衛生法による衛生管理義務
・食品衛生法第50条では、飲食店は「衛生上の危害を防止するために必要な措置」を講じることが定められています。
・具体的には、ネズミ・昆虫などの防除(ペストコントロール)が含まれており、害虫対策を怠ることは法令違反に該当します。
・2021年から完全施行されたHACCP制度でも、一般衛生管理の一環としてネズミ・昆虫の発生防止と記録管理が求められています。
②保健所による立ち入り検査・行政指導
・飲食店は定期的に保健所の立ち入り検査を受けます。
・立ち入り検査で害虫が確認された場合、「改善命令」や「営業改善指導」を受ける可能性があります。
・改善が見られない、または重大なリスクがあると判断されれば、営業停止処分に至ることもあります。
サニクリーンの害虫・害獣防除(駆除)サービス
害虫のリスクに備えたい飲食店におすすめしたいのが、サニクリーンの「害虫・害獣防除(駆除)サービス」です。
サニクリーンでは、一時的に害虫・害獣を「駆除」するのではなく、計画的に減らしていく「防除」を推奨しており、ゴキブリやネズミ、チョウバエやハトなどの害虫・害獣に対応しています。サービス導入から定期的なメンテナンス、衛生環境の改善サポートまで、豊富な技術・知識を有する「駆除×防除のプロ」が対応します。全国47都道府県に展開するサニクリーンなので、個人経営の飲食店はもちろん、全国チェーンの飲食店でも、各店舗で同じクオリティの防除サービスを提供できます。
今後の飲食店に求められる害虫駆除と衛生管理

今後の飲食店における害虫駆除と衛生管理を考えるとき、いくつかの重要な課題が浮かび上がってきます。
第一に、SNS社会への適応があります。近年、SNSの普及により、ゴキブリやネズミなど害虫の目撃談が瞬時に拡散し、飲食店の信頼が揺るがされる事例が増えています。衛生管理に力を入れるのはもちろんのことですが、今後は「トラブル発生時の透明性ある情報発信」や「誠実なクレーム対応」が衛生管理と並ぶ評価軸になると考えられます。
第二に挙げられるのが、制度対応の継続的な強化です。2021年に完全施行されたHACCPでは、飲食店に工程管理や害虫防除の記録保存が求められています。しかしながら、特に小規模店舗は人員やコストの問題から十分にHACCP対応が進んでいないのが現状です。設備投資や専門業者の定期利用にかかるコストは経営を圧迫しやすいため、効率的な「総合的有害生物管理(IPM)」の普及や、行政による支援策が今後の論点となるでしょう。
もう一つ、環境変化への対応も見逃せない課題です。昨今の気候変動により、害虫の発生時期や分布範囲が拡大する傾向が指摘されています。たとえば、温暖化によってチャバネゴキブリの活動期間が長期化しており、従来の季節的対策では十分でなくなる可能性も指摘されています。今後の飲食店には、年間を通した害虫モニタリングにより、発生傾向の変化に合わせた対策が求められるようになるでしょう。
まとめ
ゴキブリやネズミ、ハエなどの害虫は、食中毒や異物混入、行政処分や評判の低下、売上の低迷など、飲食店に深刻なリスクをもたらします。飲食店にとって害虫対策は、経営を守るために欠かせない取り組みだと認識しなければいけません。
日常清掃や衛生管理の徹底、建物環境の改善によって、害虫の侵入・繁殖を防止することが基本になりますが、自力の対策だけでは限界があります。この限界を補うためには、専門の害虫駆除業者の力が必要です。日常清掃で「発生させない」、建物対策で「侵入させない」、害虫駆除業者と連携して「再発を防ぐ」という3本柱で、害虫対策に取り組んでいただきたいと思います。
Q&A|飲食店の害虫駆除に関するよくある質問
Q.1 飲食店で特に発生しやすい害虫は?
A. ゴキブリ、ネズミ、ハエが代表的です。それぞれ繁殖力が強く、大量発生を招いてしまうとトラブルのリスクが高くなります。
Q.2 害虫はどのように店舗へ侵入してくるの?A. 排水溝や配管の隙間、窓や出入口など、建物の構造的な弱点から侵入することが多いです。ダンボールや搬入物に、害虫あるいはその卵が付着しているケースもあります。
Q.3 自力でできる効果的な害虫対策は?
A. 日常清掃のほか、排水溝やグリストラップの定期洗浄、食材の密閉保管、ダンボールの早期廃棄など、衛生管理を徹底することが大切です。
Q.4 市販の駆除グッズは飲食店でも使える?
A. はい、使用できます。ベイト剤、粘着トラップ、電撃殺虫器などは初期段階での駆除や発生状況の把握に有効です。ただし、スプレータイプの殺虫剤を使用するときは、食品や食器にかからないよう注意が必要です。
Q.5 害虫が1匹でも見つかったら業者に依頼すべき?
A. 1匹であれば自力での駆除で問題ありません。しかし、繰り返し発生する場合や多数目撃する場合は巣が形成されている可能性があるため、専門の害虫駆除業者への依頼をおすすめします。
Q.6 害虫駆除業者を選ぶ際のポイントは?
A. 資格・許認可の有無、飲食店での実績、見積もりの透明性、安全な薬剤の使用、緊急対応の体制などを確認することが重要です。
Q.7 駆除を業者に依頼した場合の費用相場は?
A. スポット契約は2万〜10万円程度、定期契約は月1万〜3万円が目安です。ただし、店舗の広さや害虫の種類、発生状況などによって変わってきます。
Q.8 害虫対策を怠るとどのようなリスクがある?
A. 食中毒や異物混入による健康被害、SNSや口コミでの評判悪化、さらには保健所からの行政指導や営業停止処分につながる可能性があります。
Q.9 HACCPにおいて害虫駆除はどのように位置づけられている?
A. 一般衛生管理の一環として、ネズミ・害虫の発生防止や駆除の実施、記録の保存が義務付けられています。
Q.10 害虫対策は季節によって工夫が必要?
A. はい。夏は高温多湿によりゴキブリやハエの繁殖が活発化し、冬は暖かい店内にネズミが侵入しやすくなります。季節ごとのリスクを把握し、年間を通した計画的な対策が求められます。
<参考文献>
※参考:HACCP(ハサップ)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
※参考:HACCP ハサップ・危害要因分析重要管理点)とは – 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000896866.pdf
※参考:公益社団法人 東京都ペストコントロール協会
https://www.pestcontrol-tokyo.jp/